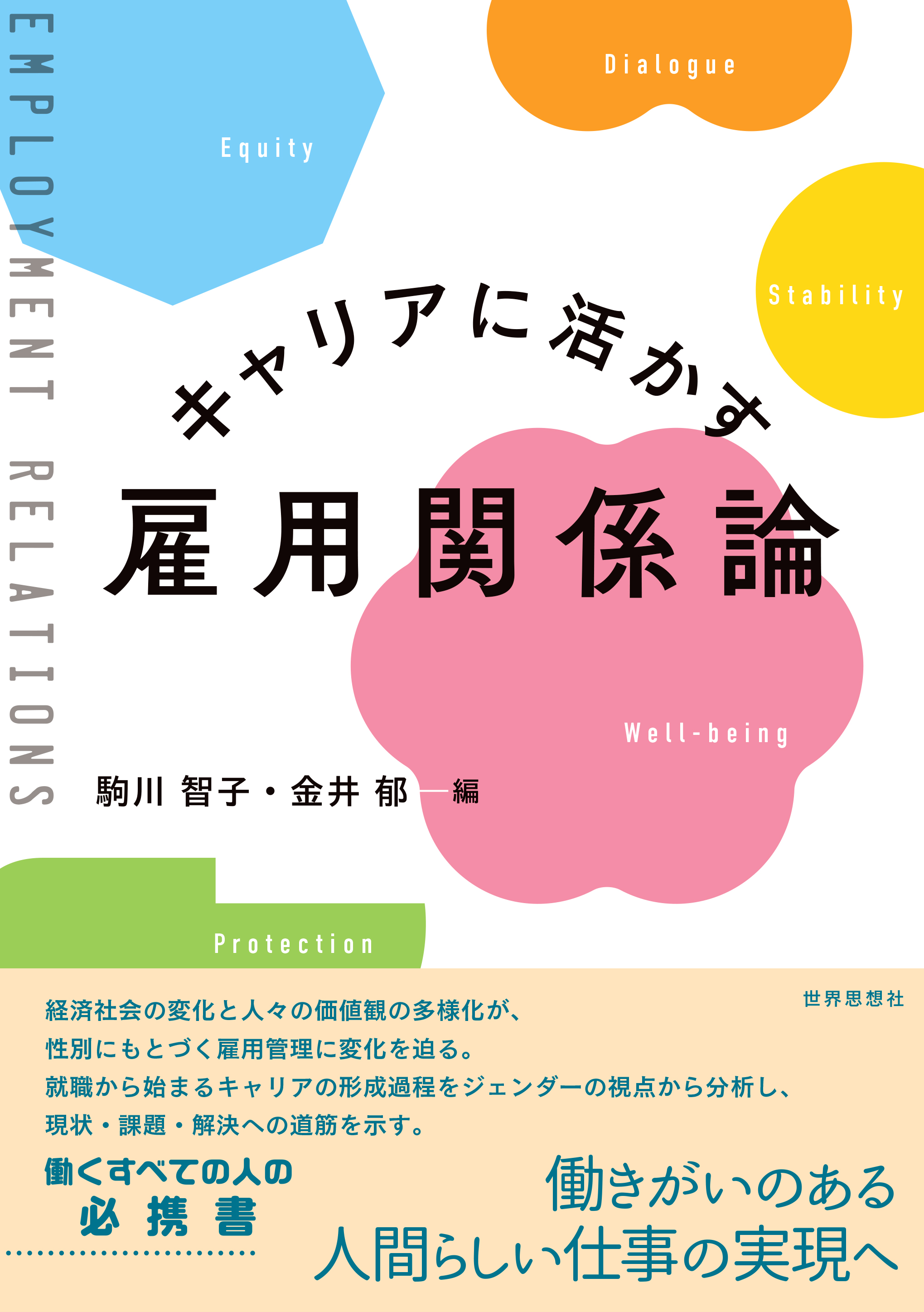個が個として生きられる社会を目指して
幸せに働き、生きることはどのように実現できるのか? ジェンダーの視点から日本の雇用をめぐるルールや慣行を明らかにした『キャリアに活かす雇用関係論』の刊行を記念し、2024年3月2日(土)にお茶の水女子大学でシンポジウムが開催されました。対面・オンライン合わせて100名が参加しました。
編者の金井郁さんによる司会のもと、「一番学生に伝えたいメッセージ」を執筆者が各章のテーマと絡めて報告しました。その後、「本書をどう読んだか」についてのコメント、全体討論を通じて、ジェンダー視点を貫く授業のつくり方、学生の興味と理解の引き出し方、男女格差が埋め込まれた構造を変えていく方法について議論しました。シンポジウムの内容を5回にわけてレポートします。
連載トップページはこちら
何度でもやり直しができる社会へ
〔林亜美/第9章:離職・転職〕
企業で実際に働いている時にどのようなことが起こるのか、つまり内部労働市場を扱う他の章に対して、この第9章だけは仕事を辞めたときの話、つまり外部労働市場を扱っているのが特徴です。辞めたときにどうすればいいのか、という知識を伝えるのは、これまで手薄だったように思います。
大学で学生たちから、「どうすれば面接を通過できますか」とか、「エントリーシートの書き方を教えてください」とか、「インターンシップに行ったほうがいいですか」等々の相談をよく受けます。ですが、会社を辞めるときはどうすればいいのかという質問はほとんど出てきません。
しかし、大学新卒の3割は3年以内に離職することが、厚生労働省の調査「新規学卒就職者の離職状況」より明らかになっています。大変な就職活動を経て就職しても、その30%は離職しているということです。誰もが離職・転職しうるということを頭に置き、そのときに備えて知識を持っておくことは大切ではないかと思います。
失業とはどのような状態を言うのか。ILOの定義によりますと、①仕事がない、②仕事を探している、③すぐに仕事に就ける、この3つの条件を満たしている人が失業者と定義されています。
いつの時点でも大抵男性の失業率のほうが高いです。なぜなら、女性は専業主婦になって非労働力化すると、失業者の定義からは外れてしまうからです。実際、コロナ禍で女性の就業者数は男性よりも大きく減っています。それでも、女性の失業率は実際より低く出ています。
この図は、男性失業者、女性失業者の失業期間別割合を1984年から2022年まで年推移で表したものです。男性は正社員であることが多いため失業しにくいが、一旦失業すると長期化しやすいことがわかります。一方、女性は非正規雇用で働いている割合が高く、失業しやすいが、再就職が早く失業期間は短いです。全体的に失業が長期化している傾向も読み取れます。

『キャリアに活かす雇用関係論』144ページより
『キャリアに活かす雇用関係論』145ページより
それでは、転職によって雇用形態は変化しているのでしょうか。正規雇用の場合には転職後も正規雇用になる割合が46.9%あります。対して、非正規雇用から正規雇用になる割合は7.2%と非常に低い。非正規から正規への転職が困難であることがわかります。
仕事を辞めたらどうしたらいいのか?「まず、ハローワークに行きましょう」と学生たちには伝えています。雇用保険受給者は、失業保険を受給することができます。そして離職者訓練(求職者支援訓練も受講可)を受けることができます。一方、雇用保険非受給者の場合は、失業保険は受給できませんが、求職者支援訓練を受講することができます。このように、次の仕事が決まるまで、テキスト等は有料になりますが、公的職業訓練を無料で受けながらスキルアップできる制度があるので、ぜひ活用してほしいです。
第9章で強調したいのは、離職・転職した人も雇用形態の差別や能力形成の機会の不利益を受けずに働ける社会を目指そう、ということです。長い人生の間で病気になったり、家族の介護が必要になったりすることは誰にでも起こりえます。キャリアのブランクがあったとしても、何度でもやり直しができる社会が望ましいと考えます。
目指すべきは働く人のウェルビーイング
〔真崎宏美/第13章:いろいろな人と働く〕
2015年にSDGs(持続可能な開発目標)が国連で採択されました。SDGsが採択されるまでに国際社会のなかで醸成されてきた、非常に大事な考え方のひとつが「ウェルビーイング」です。ウェルビーイングとは、人間が心身ともに満たされてよく生きられていると持続性をもって感じている状態のことです。
組織のなかでウェルビーイングを実現するために土台となるのは、人権の保障です。日本ではハラスメント問題などをきっかけに「ビジネスと人権」が注目されています。歴史的にみれば、国家は人びとの人権を保障していく義務があるという考え方に基づいて法律が作られてきました。しかし、グローバル化に伴って数々の多国籍企業が、特に途上国の人びとや先住民の人権を無視して搾取し、彼らの環境や生活を脅かすような経済活動をするようになりました。そこで2011年に国連は、絶大な経済的影響力をもつ企業にも、人権を保障する責任があるということを、「ビジネスと人権に関する国連指導原則」という形でまとめ採択しました。
これは非常に大きなパラダイムシフトでありました。事業の規模を問わず、自社が直接関わっている範囲のみならず、原料調達から製造・加工、購入、販売、使用、廃棄までに至るサプライチェーンにおいて、人権に関する責任が問われるようになったからです。企業の姿勢を投資家も見ています。環境、社会、ガバナンスなどの非財務情報を考慮するESG投資市場規模は拡大しています。

『キャリアに活かす雇用関係論』203ページより
働いている人たちのウェルビーイングを実現するために必要なのが、多様性という考え方です。ビジネスの文脈では、DE&I(ダイバーシティー、エクイティ&インクルージョン)という言葉が使われています。ダイバーシティーは多様性、エクイティは衡平性、インクルージョンは包摂性と訳されます。いろいろな属性の人たちが、同じ空間に、違いを良さとして生きられることが大切だということですね。
「エクイティ」の衡平性とは「同じである」ことを意味しません。私たちは、人種やジェンダー、年齢や階層、宗教、障害など、さまざまな属性を複合的にもっています。属性の違いが不利益をもたらさないよう、社会の構造的なゆがみを可視化したうえで、しかるべき配慮をしていくというのが、エクイティの考え方です。
DE&Iを進めるために重要なのが、心理的安全性を確保する取り組みと、アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)を取り除く取り組みです。どんな人も言いたいことが言える職場であるためには、自分は尊重されているという心理的安全性が不可欠です。誰もが尊重される環境をつくるには、自分たちが普段何気なく使っている言動にも異なった属性の人に対する偏見が織り込まれていることに気づくことが大切です。
日本の企業は生産性が低いと言われています。経営層、意志決定する人たちの属性が偏り、多様な人びとによって構成されている社会を反映できていないことが大きな一因であると考えられます。どのような違いがあっても、「あたりまえに」個が個として生かされるような組織を作っていきましょう。そうした組織は、コミュニケーションが豊かで、創造的なアイディアや価値を生み出す力をもっています。
〈シンポジウム登壇者〉
駒川智子:北海道大学大学院教育学研究院教授
金井郁:埼玉大学大学院人文社会科学研究科教授
筒井美紀:法政大学キャリアデザイン学部教授
禿あや美:埼玉大学大学院人文社会科学研究科准教授
大槻奈巳:聖心女子大学現代教養学部教授
申琪榮:お茶の水女子大学ジェンダー研究所教授
林亜美:神田外語大学外国語学部講師
田瀬和夫:SDGパートナーズ有限会社代表取締役CEO
真崎宏美:SDGパートナーズ有限会社シニア・コンサルタント
朴峻喜:立教大学経済学部助教
佐野嘉秀:法政大学経営学部教授
書籍の情報はこちらから
【目次】
序 章 なぜ雇用管理を学ぶのか〔駒川智子・金井郁〕
第1章 大卒就職・大卒採用――制度・構造を読みとく〔筒井美紀〕
第2章 配属・異動・転勤――キャリア形成の核となる職務〔駒川智子〕
第3章 賃 金――持続可能な賃金のあり方とは〔禿あや美〕
第4章 昇 進――自分のやりたいことを実現する立場〔大槻奈巳〕
第5章 労働時間――長時間労働の是正に向けて〔山縣宏寿〕
第6章 就労と妊娠・出産・育児――なぜ「両立」が問題となるのか〔杉浦浩美〕
第7章 ハラスメント――働く者の尊厳が保たれる仕事場を〔申琪榮〕
第8章 管理職――誰もが働きやすい職場づくりのキーパーソン〔金井郁〕
第9章 離職・転職――長期的キャリア形成の実現に向けて〔林亜美〕
第10章 非正規雇用――まっとうな雇用の実現のために〔川村雅則〕
第11章 労働組合――労働条件の向上を私たちの手で〔金井郁〕
第12章 新しい働き方――テレワーク、副業・兼業、フリーランス〔高見具広〕
第13章 いろいろな人と働く――SDGsによる企業の人権尊重とDE&Iの推進〔田瀬和夫・真崎宏美〕
終 章 労働の未来を考える〔金井郁・駒川智子〕
より深い学びのために
索 引