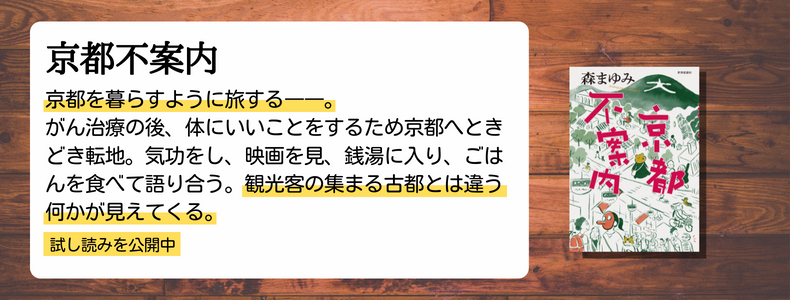はじめに
京都を暮らすように旅する――。
還暦を過ぎて、ふたたび京都に通うようになった。
それまでは、仕事で行っても、ゆっくり滞在しないですぐに帰ってきた。ホテルも高いし、食べ物屋も高い。名所旧跡は混んでいる。もうひととおり見ちゃったしな。それも今よりずっと空いている、風情のある時代に。それに私は京都がなんとなく苦手だった。理由は判然としない。しかし、大きな病を得て、私は京都で樹木気功をやることにしたのである。その話はまたあとで。
初めて京都を訪れたのは一九六七年、中学に入る前の春休みだった。
東京オリンピックに合わせて一九六四年、新幹線が大阪まで開業した。父が、新幹線で奈良と京都に行こうといい出した。それは父らしい、一泊二日のウルトラ盛り込みすぎの旅で、タクシーを貸切り、一日に一〇くらいもお寺を訪ねた。訪ねたというより回ったといった方がいい。初日は奈良の東大寺や興福寺を見学、京都に移動し古い旅館に泊まる。母が「京間というのは広いのねえ」と驚いていたのを思い出す。たしかに、空襲で焼け出され、東京の長屋を改造した家で歯医者をやっていた母に、あの旅館の八畳と一〇畳の二間続きはずいぶん広く見えたに違いない。その旅館には古い匂いがした。何もかも、人の話もいさかいも、吸ってしまった感じだった。
京都では清水寺、金閣寺、銀閣寺、龍安寺の石庭、苔寺とも呼ばれる西芳寺、泉涌寺を覚えている。あとは忘れた。西芳寺の美しい苔に惹かれた。運転手さんが湯葉料理の店に案内してくれた。生まれて初めて食べる湯葉、そんなにおいしいものでもなかったが、珍しくはあった。そしてその日のうちに新幹線に乗って帰ってきた。
中学に入ると、平凡社の『太陽』という雑誌を集め、『源氏物語』や『枕草子』『方丈記』『徒然草』などを読むようになった。『古事記』や『日本書紀』もお小遣いで岩波の古典文学大系をそろえて読み始め、やっぱり日本の文化は西高東低なんだな、と納得した。歴史の厚みが違う。
『源氏物語』を読むのに一番役に立つガイドブックは、池田亀鑑『平安朝の生活と文学』(角川文庫、一九六四年)。唐の長安を模して造られた京都の街の構造、後宮の制度や役職、さらに御所の中の地図、寝殿造の説明、宮廷の食事や寝具などについて細かく書いてあった。
小学生の頃に読んだ『源氏物語』は子ども向けの翻案もので、性的なことはいっさい隠されていた。光源氏が父桐壺帝の妃である藤壺中宮と密通して冷泉帝が生まれ、罪の意識におののく、などというところは理解できなかった。それでも、少女の紫の上を源氏が引き取って育てるところや、生き霊に祟られた夕顔の不思議な死とか、関係する女性たちに着物を選んで贈るところなどは、十分エロティックで興奮した。
古典を原文で読むようになったのは中学から。また判官贔屓もあって、紫式部よりは、若くして亡くなった中宮定子に仕えた清少納言の方がさっぱりして好きだった。ともあれ子どもの頃に暗唱したものは忘れずに根付く。「春はあけぼの。ようよう白くなりゆく山際、…」「仁和寺にある法師、…」「音のかそけきこの夕かも」というようなフレーズは、世界のどこにいても風景とともに思い起こされる。この前も、エチオピアに行ったとき、夕暮れの鳥の群れに「烏の寝所へゆくとて…」と思ったことである。
高校に入ると、ユースホステルの会員になり、レンタル料を浮かそうとシーツをリュックに詰め、東山ユースホステルに泊まっては京都の寺を訪ね歩いた。京都大原の三千院を舞台にしたデューク・エイセス歌う「女ひとり」が流行っていた頃だった。節約のため、行きは夜行の椅子席。早朝に着くと清水への坂を白い息を吐きながら登って行く。野に朝もやがかかって『徒然草』の「あだし野の露 鳥辺山の煙」という一節を思い出す。嵯峨野の念仏寺や落柿舎の辺も歩いた。
ガイドブックにある店で湯豆腐を食べたら、翌日は公園でパンをかじる。そんな貧乏旅行に妹を連れて行ったら、あまりの強行軍に奈良の箸墓古墳のあたりで泣き出され、往生したことがある。
お正月に行ったとき、丸もちの白味噌雑煮が出て、衝撃だった。東京の雑煮は醤油仕立てのすまし汁で、鶏と小松菜、椎茸くらいしか入っていない。そして角もちである。あんな甘ったるい雑煮があるとは! 総じて京都の味は私には薄い。
初めて京都でうどんを食べたときも驚いた。「うどんが透けて見える」と。ニシンそばもそばが透けて見える。ずっとあとで、文化庁長官だった河合隼雄さんと対談したとき、「まあ、東京の人はよくあんな墨汁みたいなそばを食べはりますなあ」と逆の衝撃を語られた。
くずきりとかいう甘味も、不思議な食感だった。正直いっておいしいとは思わなかった。湯豆腐もイマイチだし、ちょこちょこ詰め合わされた松花堂弁当とかいうものも、さしてうまいとは思わない。海老芋と棒鱈の炊き合わせ、いもぼうとかニシンそばも、海から遠い盆地での保存の苦労を表すものなのだろう。「芋一筋に何百年も炊いておいやす。えらいことですなあ」と京都の人はあまりえらいこととは思っていない調子でいう。
京都のガイドブックにやたら書いてある「一見さんお断り」という文字が怖かった。京都の老舗では、初めての客を相手にしない。「売ってもらえないこともあります」と書いてさえあった。それと「ぶぶ漬け神話」。京都のお宅で「ぶぶ漬けでもどうどす」と勧められたら、たやすく乗ってはいけません。「そろそろ帰っておくれやす」という合図だから、というのだ。
これもずっとあとになって、日本中世史研究の脇田晴子先生に聞いたところ、「それは祇園祭の氏子圏あたりの話やね。京都大学周辺は各地から人が集まるから、そんなしきたりはないでしょう」とのこと。しかし、「ぶぶ漬け神話」は、東京の私たちにはいまだに強く信じられている。言葉に裏のない東京では、「お昼だからチャーハンでも作ろうか」「あら、ありがと」、「ラーメンの出前とる?」「いいわね」ですむのに…。
そういえば高校三年のとき、私は京都の北の方、一乗寺にある級友の親戚の家に泊めてもらったことがある。広い池の向こうに門があり、その門を入ると立派な庭があり、障子戸の玄関があり、玄関の間で出迎えを受けた。そこから廊下を何度も折れて、泊まるべき客間に案内され、上生菓子と抹茶が供された。一五坪の長屋育ちの私は仰天した。そのおじさまは何日か仕事を休んで、私たちに京都を案内し、おいしいものも数々食べさせてくださったのである。
ともあれ、京都は成長期の私の美的、文学的な生活の中では中心を占める存在であった。
芥川龍之介の『芋粥』で、京都の下級貴族が「一度でいい、芋粥を腹一杯食べてみたい」と願い、地方の豪族のところに行くと、都では高価で手に入らない芋を山のように積み上げて食べさせようとするくだりがある。『今昔物語集』由来の小説だが、そこには舌の肥えた東京下町っ子・芥川の、京都の食べ物に対する皮肉が効いているような気がする。そういえば、芥川の『鼻』や『羅生門』も京都への想像力をかきたててくれた作品だ。
高校生の私は、谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』、川端康成の『美しい日本の私』なども読んで、日本の文化について考えたりした。
しかし彼らの小説を読むと失望する。高校の頃は、川端康成はノーベル文学賞を受けた現役作家で、『古都』とか『美しさと哀しみと』なども読み、その当時は北山杉など京都の風物に憧れたが、今読むと爆笑してしまう。たとえば『美しさと哀しみと』は五〇代の作家が特急「はと」に乗って、二四年も前に別れた京都の昔の恋人に会いに行く話である。当時一六歳の少女を、三〇代の作家は妊娠させるが(未成年淫行)、早産で赤ん坊はすぐに死ぬ。女は自殺未遂をはかり、精神病院に入る(鴎外の『舞姫』みたい)。その後、日本画家となった今も独身のその女と再会し、除夜の鐘を聞きに行く。三〇代のいい女ぶり、そして今も彼女は彼を思慕している。しかも彼の作品で一番読まれ続けているのは、かつての恋を描き、妻にタイプさせた作品。なんと虫のいい話だろう。
谷崎潤一郎の『細雪』は戦争中の話だとはずっと後まで気づかなかった。ひとつも戦争の影がない。芦屋の蒔岡家のお嬢様方は、芝居や花見に何を着ていくか、何を食べるか、私から見ればどうでもいいことをいつまでも話している。花見のコースは南禅寺の瓢亭で夜食、都をどりを見て祇園の夜桜、麩屋町の旅館に泊まって、あくる日は嵯峨野から嵐山に行き、中之島のかけ茶屋あたりで弁当を開く。いいご身分ね、というしかない。この小説が、「戦争への消極的抵抗」と賞賛されたり、何度も映画化されるのにも驚く。
とはいえ大学受験のときに受けたかったのは京都大学だった。長年、京都大学で教えておられた吉川幸次郎先生の『唐詩選』が当時の私のバイブルだったし、その弟子である高橋和巳が小説家として一世を風靡しており、『悲の器』から『生涯にわたる阿修羅として』まで読みふけっていたからである。しかし父親に「なにもそんなに遠くまで行かなくても近くにいい大学があるじゃないか」と反対され、しかも国立の数学の問題にはまったく歯が立たなかった。
大学一年の秋、友人数人で京都に行った。寒い中で鞍馬の火祭を見て、山から下りてきて泊まった小さな宿のすばらしかったことを忘れない。遠くに灯った小さな看板、典型的京町家、お湯を沸かし、色とりどりの浴衣をそろえてくれた女将の心配り、朝ごはんのだし巻き卵のおいしかったこと。ここも一見さんはお断りの宿で、友人のお母さんの紹介だった。
それを最後にずっと京都とは縁がなかった。
結婚し、子どもが次々生まれ、シングルマザーとなって食べるのが精一杯で、京都に遊ぶ暇もお金もなかった。研究会や仕事で行っても、用が終わるとすぐに新幹線に乗って帰った。あらゆる小説や映画、流行歌などで作られた京都イメージを、私は素直にのみこめなくなっていた。
一九九〇年に全国町並みゼミの京都大会が行われたとき――すでに三〇年以上前になるが――、京都の町は高校時代に訪れた一九七〇年代初頭とはかなり違ってきていた。木造下見板張り、格子戸、瓦屋根の京町家はその頃から減りはじめ、狭い小路に、奥歯に物が挟まるようにマンションが建設された。さらに、観光立国推進によるインバウンド政策が始まって以来、外国人で混雑する京都は、私の苦手な町となった。
ところが二〇一五年に大きな病を得て、治療の後、自分で少しは体のメンテナンスをしなければならなくなった。そのときに思いついたのが、Nさんという治療家である。彼は週に何度か、京都のある場所で朝の気功の会を開いている。参加したらどうか、と友人が勧めてくれた。私の京都通いがまた始まった。

目次
はじめに
第1章 樹木気功で体を治す
第2章 バスと自転車
第3章 ゲストハウスとアパート探し
第4章 カフェとシネマ
第5章 がらがらの京都
インタビュー① 法然院貫主・梶田真章さんに聞く――学びの場としてのお寺
第6章 散歩で建築を楽しむ
第7章 古都の保存と開発
第8章 宿の周りでひとりごはん
第9章 京料理屋の大忠にて
第10章 吉田山の話
インタビュー② 女性史・生活史研究の西川祐子さんに聞く――偶然を必然に変えて
第11章 鴨長明『方丈記』と「足るを知る暮らし」
第12章 子規の京都
第13章 吉井勇と祇園
第14章 漱石の女友達・磯田多佳
インタビュー③ 染織家・志村ふくみさんに聞く――“見えないもの”に導かれて
第15章 つたちゃん、たねちゃんのこと
第16章 ヒッピーとタイガース
第17章 居酒屋で聞く話
第18章 五代友厚と二人のスリランカ人
インタビュー④ 田中ふき子さんに聞く――農婦として六〇年
京都リヴ・ゴーシュ――あとがき