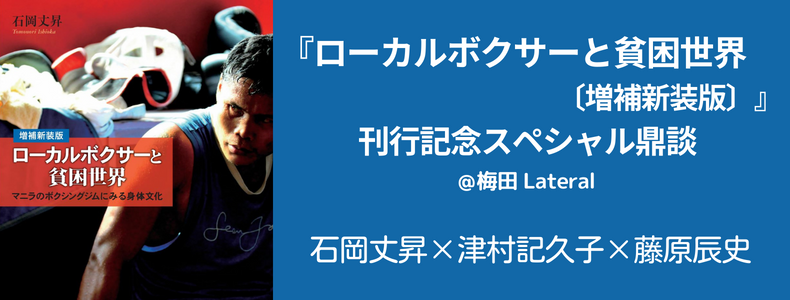関係を精算しない社会
『ローカルボクサーと貧困世界〔増補新装版〕』の刊行を記念して、著者の石岡丈昇さんに加え、
ボクサーたちの生活世界をつぶさに観察した本書だからこそ、
前編はこちら
ご飯とお金がつながりをつくる

左より、藤原辰史さん、津村記久子さん、石岡丈昇さん
津村 この本って当然、本当に起こったことを書いているノンフィクションなんですが、小説で書かれたとしても十分面白いところがたくさんあるなぁと思ってたんです。それは、「わかるわかる!」ってなる場面なんですよね。
私にとってはカピットバハイ(注:近所に住む仲間たちを指す言葉。第5章2―5に記述)についてのところで。自分がご飯作るじゃないですか、そんでうちの家だけで食べたいんやけど、一応近くに通った人に「食べる?」って声かけるみたいな文化ですよね。あれなんかおもろいなって。
他にも、マネージャーがボクサーに対して感じる負い目みたいなんもそうですね。マネージャーは立場が上なんですけど、体を使ってるのはボクサーだっていうので、ボクサーに負い目を感じちゃう。彼らはお金で繋がってるだけの割り切った関係ではないんですよね。「お金を払ってるから」って関係性をフラットにするんではなくて、常にどちらかに負い目がある、非対称な状態にすることが大事なんだと。
カピットバハイでも、「こないだ食べさせたし、今日はええやろ」みたいな形で関係を精算しないですよね。こんな感じで、非対称な、つまり「もちつもたれつ」みたいな関係にしておきたいっていう感覚とか、すごい日本人みたいやなって思ったんですよ。
石岡 向こうでは自分の持ち物を自分に閉じておくと、「ケチだ」って言われるんですよ。そして、「ケチ」って言われることは道徳的によくない、という感覚がある。「自分は役目を果たしてない」という感じなんですかね。
津村 たとえば今の日本やと、「自分のお金は自分のためだけに使う」ってなんも悪くない考えじゃないですか。だけど彼らはそうじゃないんですよね。お金持ってる人には、周りの人が「あの人気前がいいからさ!」って、ほんとに思ってるかどうかわからないけど言いまくって、お金をちょっとずつ出してもらうような、なにか有機的な感覚があるんですよね。自分が持ってるものから、どんどん漏れ出していくような。
石岡 スクオッターでご飯作ってるときは、前を人が通ると「なんか食べた?」って言わなきゃ、という感覚があるんです。心の中では「食べる食べる!」とか言われたくないなって思ってるんですけど。
若い頃はパソコンを持ち込んで調査してたんですけど、原稿を書いててもボクサー達がわらわらやってきて、「音楽をかけろ」「写真を見せろ」って言ってくるんですよね。原稿なんか書けたもんじゃなかった。
どういうことかというと、「自分はこうだから」って言って自分の取り分だけをガッチリ守るみたいな形の生き方ができないんですよね。「自分の時間」とか「自分の持ち物」は自分のなかで閉じるんじゃなくて、与えて与えられるのが当然、という前提の中で生きてるんだと思います。
藤原 「たかる」というのは大事な言葉だと思います。「集る」って書いて「たかる」と読むらしいんですよ。日本語で「たかる」って言うと、なんとなく権威のある人のもとに群がるようなイメージなんだけど、そうではなく津村さんが言ったように、もらう側も与える側も微妙な磁場の中にいる感覚がいいですよね。
関係性を精算しない
津村 お金で切り離されている関係より、どこか豊かさを感じるんですよね。「お金があって偉いんだ」じゃなくて、数値化されない、「あの人いい人やんな」っていうのを周りが言う感じ。でも、それってめっちゃ複雑なシステムですよね。村社会的な嫌な関係とも、少し違う。そこがなんか面白いなって思って。
「関係性が精算されない」というのが大事なんかなとも思うんです。彼らは関係を精算しようとすると「精算すんな!」って怒り出すんでしたっけ?
石岡 そうですね、「精算」とか「ご破産」みたいな、「はい、これで終わり!」みたいなのはすっごい評判悪い。
あるアメリカ人のマネージャーが、ボクサーのファイトマネーを管理して、引退のときに今までのファイトマネーを退職金として払う仕組みを作ろうとしたんですね。でも、それは評判が悪かった。ボクサーにとっては、ただ単に「お金を管理できない人だ」ってみなされるだけじゃなくて、引退した後にマネージャーになにかの相談に行っても「いや、俺はちゃんと手切れ金をお前に渡したやないか」って言われちゃうんですよ。関係を切る、精算してご破産にしちゃうようなカードに使えてしまうんですよね。
津村 貸し借りがコミュニケーションになってるっていうのが面白いですね。お金借りっぱなしとかお金貸しっぱなしとか、普通やったら嫌じゃないですか。でもそれも繋がりの1つとして捉えてるのがすごい。「あれ返してよ」とか「あれ返すからさ」っていうので人に会う機会ができて、コミュニケーションが成り立ってる。私たちもやってることやけど、それを上手く拾い上げてますよね。
藤原 私、現代史概論という講義で、いつも最後の時間に「『今までの歴史の中で、これだけは商品にしなければよかったもの』は何だと思いますか」と質問するんですよ。で、どの大学でもいちばん多い答えが「人間関係」なんです。それだけ、人間関係を作ることが商品化していってるんだと思います。
人間関係がお金を出して繋がるようになってきてしまった。でも、石岡さんのは真逆の話で、人間関係はわざわざお金で「買う」ようなものではなくて、作り出していくものなんだと。
「ただいる人」がいる
津村 みんなめっちゃ距離近いなっていうのも面白いんですよね。お金なくなったら、知り合いの家にぽんと住み込んじゃったりするじゃないですか。私やったら絶対嫌やな……って人でも泊めちゃったり。
石岡 「プライベートな空間」っていう概念がちょっと違うんですよ。とにかく密集してるんです。夕飯の匂いもだだ漏れですし、人も押しかけてきちゃうし。そういう中で、パブリックとかプライベートとかの概念が、我々とはだいぶ違うような感じで捉えられてる。
そこで暮らすボクサーたちを見てると、「この人たち、誰とでも生活できるんだな」って感じるんですよね。暮らしを続けていくうえで、それも一つの強さだなと思います。
津村 誰かを受け入れることで生まれることもありますよね。家の中をプラプラしてる稼ぎがない人がおっても、子守を任せるとかの役割ができたり、Eジムの中になんとなくおったら仕事が回ってきたり。こういう「自他が分けられすぎてない」感じが、もっと自分の周りの社会に増えればいいのにって思いました。
石岡 大学とか会社でもそうですけど、普通は「いかに人数を減らすか」って考えるじゃないですか。「この業務はもっと人減らせるな」みたいな。Eジムは全然逆で、「常に余ってる」んですよね。どうせ大鍋でご飯作ってるし、寝る場所だったらそこらへんにあるから、いろんな人が居られる。でも、そういう人たちが「じゃあ今度興行するし、ボクシングリング作るから、ちょっと手伝ってくれ」と言われると「はい!」ってやってくれたり。何かしてくれればいいし、少なくとも話し相手にはなる。
津村 そういう「ただいる人」って、今はあんま周りにおらんですよね。
石岡 そうですね。ジムにはそんな人がいっぱいいたんで、最初はボクサーみたいな見た目の、「ただいる人」を見分けるのが大変だったんですよ。
尽きなく在ろうとする意思
津村 石岡さん、めっちゃボクサーたちに相談されてませんか? 自分の奥さんが出ていこうとしてるボクサーから奥さんを引き止めるよう頼まれたり、恋愛相談に乗っちゃったり。日本から来た学生さんの扱いじゃないですよね。
藤原 石岡さんのすごいところは、研究対象から相談を受けちゃうことですね。私がナチスから相談を受けることは絶対にないですけど。農家さんとかから相談されることもあまりないです。
石岡 彼らも僕も若かった、っていうのはあった気がしますね。
住み込み調査をしていた頃、いちばん小さいミニマム級のボクサーがいたんですけど、彼に好きな女の子ができた。その女の子の誕生日、彼はどうすればいいかよく分からなかったみたいで、プレゼントに豚肉を持ってったんですよ。マーケットで買った生のやつ。「そりゃダメだぜ!」ってみんなで笑いました。
離婚の話からこういう話まで、ボクサーたちの恋愛模様は色々です。そのうえ、生活も苦しい。小学校もドロップアウトしてたり、生きていくのがとてもしんどい立場なんです。でも、彼らがいるのは「ボクシングで勝ちたい!」とか「あの子と付き合いたい!」とか、「自分はこうありたい」と思う小さい夢がたくさん詰まってる世界だなと思ったんですよね。
貧困や肉体労働のことを調べようとすると、僕も「1試合の収入がいくらで…」とか、数字で考えてしまうんですよね。それはとても重要なことなんですけど、でも同時にもう一方で、その人たちがどういう夢を描いて、どういう自分でありたいと思っているのかを見てみたいなと思ってたんです。
津村 最後に書かれた、「尽きなく在ろうとする意志」っていう言葉がそれを表していると思うんです。すごく残るんですよね、この言葉。
フィリピンのボクサーたちの人生と、日本の私たちの人生には直接繋がりがあるわけではないんですけど、やっぱり勇気が出るんですよね。こういう諦めなさもあるんやとか、こういう受け入れられ方もあるんやとか、こういう人どうしの関わり方もあるんやとか。
チャンピオンになれなくてもなれないなりの人生があって、ボクシングを辞めたとしても辞めたなりの人生があるんだって、そうやって彼らの人生を見ていると、どんなふうにでも生きていけるような気がしてくるんですよね。
この本は落ち込んでる人に読んでほしいですね。もう自分には友達もおらんし、お金もないし、何も持ってないって思う人は、ちょっと読んでみたらと思います。いろんな人生があって、いろんな人との繋がり方があるって思えるし。
藤原 私ももうまったく津村さんと同感です。逆に、今の日本で生きていくことは、人間関係が豊かだとかっていうことよりかは、やっぱり「富をどうやって蓄積するか」に偏ってるんだなと思わされました。
これ読んだ後、なんか生きてこうと思いましたよね。もうちょっと生きてこうって。 「生き方ちょっと尽きてないな」みたいな。
石岡 藤原さんと津村さんのコメントで、あぁ僕はそういうことをやりたかったんだと実感してます。どうもありがとうございます。
購入は【こちら】から
【目次】
序 章 ローカルボクサー世界から
1 ローカルボクサーの社会学
2 貧困世界とのつながり
3 住み込み調査と身体文化への着目
第1章 ローカルボクサーの身体文化への方法的接近
1 ローカルボクサーへの接近
2 第三世界スポーツ論の問題構制
3 「スポーツ社会学のための計画表」と二重のフレーミング論
4 マニラ首都圏のローカルボクサーへ
第2章 ボクシングジムの空間構成
1 Eジムのボクサーと非ボクサー
2 Eジムのコンテクスト
3 ボクサーの属性
4 〈全体的空間〉としてのジム
第3章 ボクサーになる――集団競技としてのボクシング
1 ジムの日常の深みへ
2 ボクサーになる
3 ジムワークにみる実践理性
4 サクリフィショという倫理
5 女性の排除形式
6 集団競技としてのボクシング
第4章 ボクシングマーケットの構造――敗者の生産の仕組み
1 ボクシング試合と敗者の生産
2 試合をめぐるボクサーの性向
3 ボクシングマーケットの政治経済
4 国際試合の交渉過程と「敗者の生産」
5 ボクシングキャリアの分類化
6 社会的選別と身体のトレード
第5章 互酬性の中のボクサー身体――引退ボクサーの日常
1 引退ボクサーの日常へ
2 スクオッターを生きる
3 スクオッター生活の窮状
4 引退ボクサーの暮らし
5 互酬性の中のボクサー身体
終 章 裸一貫のリアリティへ
1 ローカルボクサーの生活実践
2 裸一貫のリアリティを見据えた身体文化研究へ
後 章 その後のボクサーたち
1 ラフィ――単身での子育て、そして料理人へ
2 ステラ――フィットネスジムの運営を軌道に乗せた敏腕経営者
3 ロセリト――フィットネストレーナー、妻子の移住、女子ボクシング
4 ロイ――総合格闘技、中国への移住
5 ジェイソン――日本への移住
注/あとがき/増補新装版あとがき/図表一覧/文献/索引
解 説 時間/身体/人生 (岸 政彦)