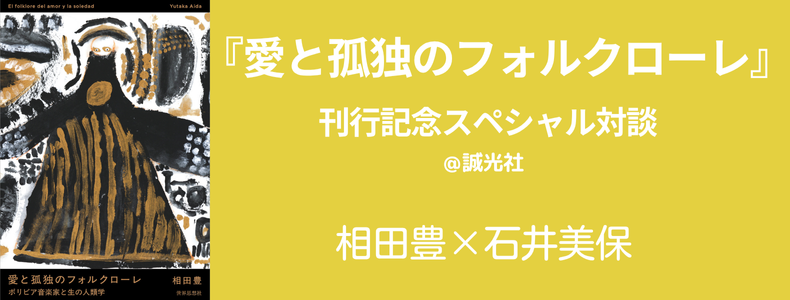
相田豊×石井美保 『愛と孤独のフォルクローレ』刊行記念スペシャル対談
『愛と孤独のフォルクローレ』の刊行を記念して、著者の相田豊さんと文化人類学者の石井美保さんによるトークイベント「聴くこと・書くこと・共にすること――フォルクローレと文化人類学の饗宴」を行いました。つながりの裏にある複層的な孤独、そしてアネクドタ(噂話、逸話)を通じた人と人との関係性など、本書の論点を深める充実の対談、前編・後編に分けてお届けします。
タグ
著者略歴
関連書籍
ランキング
せかいしそうからのお知らせ
- イベントレポート「小山内園子×中野円佳『働きたいのに働けない私たち』刊行記念トーク」を公開します!
- イベントレポート「相田豊×石井美保『愛と孤独のフォルクローレ』刊行記念スペシャル対談」を公開します!
- 連載 森千香子「モザイク都市ブリュッセル」が始まりました!
- イベントレポート オンラインイベント「中東を学ぶ――研究者が語る経験と魅力」を公開します!
- 連載 伊藤亜紗×瀬尾夏美「《往復書簡》聴いちゃった体」が始まりました!
- 特集 松岡亮二「『凡庸な教育格差社会』で」を公開します!
- イベントレポート「『キャリアに活かす雇用関係論』刊行記念シンポジウム@お茶の水女子大学」を公開します!
- イベントレポート「駒川智子&金井郁&川村雅則『キャリアに活かす雇用関係論』刊行記念トークイベント@札幌・紀伊國屋書店」を公開します!
日本との関係が深まるいま、東南アジアの必須知識がわかる入門書
東南アジアを学ぶ人のために
詳しくはこちらスポーツ文化という広大な沃野をどのように耕し、次代へと受け渡していくべきか――
スポーツ・クリティーク
詳しくはこちら「最終章まで読み通してほしい。必ず震撼するから。」東畑開人さん推薦
絶望と熱狂のピアサポート
詳しくはこちら




