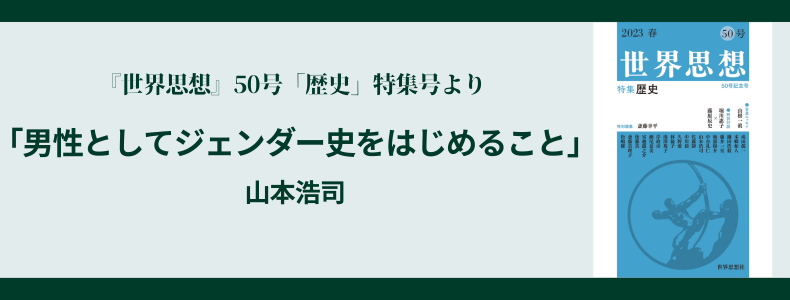男性としてジェンダー史をはじめること
PR誌『世界思想』50号「歴史」特集号より、歴史学者の山本浩司先生の「男性としてジェンダー史をはじめること」を公開します。経済史の研究者である山本さんは、なぜジェンダー史を研究するようになったのか。研究と生活、今と過去を行き来する、渾身のエッセイです。
――歴史とは、歴史家とその事実のあいだの相互作用の絶えまないプロセスであり、現在と過去のあいだの終わりのない対話なのです。
E・H・カー『歴史とは何か 新版』
――個人的なことは政治的なことだ
フェミニストスローガン
二〇二一年四月末のある日、僕は足早に最寄りの大型書店に向かっていた。脇目もふらずに入口を通過する。「女性」「出産経験」「子育て」「ジェンダー」……手当たり次第に思いつくキーワードを店頭の検索用端末に入力する。今、女性として日本で子供をもうけるって一体どういうことなんだ? お母さん向けの本じゃないんだ。出産や子育ての経験を男の僕にでもわかるように説明してくれる本はないのか?
今考えると都合のいい話だ。女性に向けて書かれた本を読めば、そこから母になろうとする女性たちの希望と期待、社会からのプレッシャーだって理解するきっかけが得られたかもしれない。書店にない名著もある。図書館に行って調べるのが当然の手続きだ。でも、それすら思いつかなかった。一緒に住み始めたばかりの相手とケンカした直後だったから。そう、僕はパートナーのYと口論になったばかりだったのだ。
「神経質すぎるんじゃない?」
コロナ禍での同居生活は特別なものだった。生活のリズムを揃え、ともに食べ、机を並べてはたらく生活が始まった。製薬会社がワクチン開発を急いでいた頃の行動制限は、僕たちの関係を親密なものにした。そのうち中古マンションでも買って腰を据えられたら。その次は家族が、子供がほしい。淡い期待と憧れとでもいうのだろうか。そんなことをぼんやりとだけ考えていた僕は、一緒にバカ笑いすることがあっても現実的なところのある彼女の考えを、理解できなかった。
女性として地方都市に生まれ、大学卒業後に就職し長い海外生活を経て今なおキャリアを積む彼女にとって、情報収集はお手のものだ。その彼女が「子供がほしいとは思えない。考えれば考えるほど『無理だ』と思ってしまう」と言うのだ。
「もっと楽観的になってみればいいのに」
「あなたは、なにもわかってない」
「……」
「○○区の制度調べたことあるの? ひどい方なんだよ? どの区の子育て制度がマシか、調べたことある? 職場の育休制度と運用実績はどうなの?」
「……」
「あなたが子供ほしいって知ってるから、私調べてみたの。調べた上で、『無理だ』『支援する気、ないんだ』って感じてるの」
「……」
僕はまともに応答できなかった。ネット検索もろくにしたことがなかったのに「神経質すぎるんじゃない?」などと言ったかもしれない。自治体が違えば子育てへの行政支援制度が違うことも僕はほとんど知らなかった。それでいて、子供を産みたいとは思えないという彼女の感じ方にこそ問題があるかのように振る舞ったのだ(賢明な読者は同じように彼女の感じ方を責めることはしないだろう)。
自分は何も知らなかったのか? 社会と世界に関心を持っていたはずの自分が、出産と子育てについては知ろうとする必要すら感じてこなかったということなのか? ケンカ別れが突きつけた問いに動揺した僕は、笑いと柔らかな物腰を引っ込めて仁王立ちする彼女に怖気づいて、家を飛び出した。こうして性差とジェンダーをめぐる問題は、四月のある午後、僕自身の切実な問題になったのだ。
あの時本屋で買った大沢真理の『企業中心社会を超えて――現代日本を〈ジェンダー〉で読む』(岩波書店)の第二章で見つけた一節がグサリとくる。「すなわち、『一般』として語られる『性別』抜きの『労働者』は、実は、人間の生活に不断についてまわる家事労働の負担を妻に転嫁した男性世帯主、という極めて『特殊』な存在に過ぎない」。
ジェンダーについての不都合な真実は、私生活だけでなく研究者としての活動とも深く関わっていた。資本主義が発展するイギリス社会での「人々の経験」に関心を寄せていると言いながら、そこでいう「社会」や「人々」は男性を前提にしていたのだ。
研究者としてもこのことと向き合わないといけない。そう考えた僕は、自分のノートやこれまでの研究を振り返るなかで、これまで見落としていた小さな論点らしき何かに気がついた。それが洗濯のこと、英国チャールズ一世の統治下の独占政策のもとで、新たに製造・販売された粗悪な石鹸の使用を余儀なくされた洗濯婦たちのことだ。
洗濯婦の声を無視したエリート男性たち
テーブルクロスや下着や首襟、さまざまな場面で使われた麻布を日頃から白く清潔に保つことは、近世イギリスを生きた男女にとって切実な事柄だった。宗教的純真さをも象徴したその白さを担保したのが、石鹸と、女性たちが大部分を担った洗濯だ。その石鹸の生産が、チャールズ一世の統治下、一六三二年に独占企業の管理下におかれる。
イギリス国内の森林は古くから広葉樹が中心で、それら硬質な樹木を燃やして作る灰汁はアルカリ性が高く、石鹸には本来適していなかった。そこで、イギリスの石鹸の多くは、アルカリ性がより低い灰汁が得られる針葉樹が広大に分布するヨーロッパ(特にポーランド・リトアニア)で生産された輸入灰汁を原材料としてきた。
輸入削減をめざすいわゆる重商主義的政策を後押ししたチャールズ一世は、大陸に広く分布する針葉樹から作られる高品質の輸入灰汁の使用を禁止し、低品質の国産新型石鹸を押し付けた。この新型石鹸が女性たちの手指にひどい手荒れを起こしたのだ。
この石鹸独占を、使用者である女性たちの視点を踏まえて分析した研究を見つけることができなかったことに、僕は驚いた。先行研究の多くは生産者側である男性石鹸工の労働の自由とその侵害に注目していた。賃労働としての洗濯に携わった女性は無数にいたことが想定できるが、彼女たちが残した記録は見つかっていない。だから、これまでの研究者は彼女たちの経験に注目することが少なかったのだ。
僕は政治家や独占に関わった男性たちが残した史料のなかに女性たちの痕跡を探すことにした。一六三四年に石鹸独占に反対する請願書に署名した三人の女性の名前を発見することができた。さらにそのうちの一人、エリザベス・タッカーの生活状況については、幸運にも詳しく知ることができた。
彼女はテムズ川沿いの貧しい教区に生まれ育ち、二九歳で結婚。二九歳までにはロンドンの女性たちの七割以上がすでに結婚していたので、当時としては晩婚と言える。反対の署名をした時は三五歳で、(存命であれば)四歳の子供がいたはずだった。しかし生活は苦しく、二年後の一六三六年の夏に黒死病が流行した時には健康状態もすぐれなかった。
貧しい病人だからこそ、死にゆく患者たちの世話という過酷な仕事を地元教区の世話人からあてがわれていた。後に感染者の遺族が関わった裁判に証人としてよばれ、彼女は当時の法慣習に従って自らの出自や生計の立て方などについても証言を残していた。そんなロンドンでも最下層の女性が、政府の後押しを受けていた石鹸生産の独占に反対する署名をしていたのだ。
エリート男性たちは手紙や議事録のなかで洗濯婦たちを「不満ばかり言う」「無秩序な」「手に負えない女ども」と書き残していた。タッカーのような女性たちは反対の署名に飽き足らず、ロンドン市長への直談判を試みたらしく、その時の様子が男性たちのあいだでうわさ話になっていたこともわかった。曰く「市長は、王の命令により臆病を厳しく叱責されたという。新型石鹸に反対して嘆願書を送った女性の一群(a troop of women)に恐れをなした、というのがその理由だ」。このうわさは、数週間後には、ロンドンから南西二〇〇キロメートル離れた小さな町に住む男性の日記にも記されていた。
ジェンダー史研究者が繰り返し指摘してきた通り、当時の社会では女性たちの言動をコントロールできることが「男らしさ」の証拠であるとされた。つまり、森林生態系という環境要因にも根ざした女性たちの抗議の声を、国益を優先したチャールズ一世とその側近たちは「無秩序な女たち」の不満であると書き換え、その女性たちの大群に怖気づいたロンドン市長を男らしさに欠けた「臆病者」と罵りながら国策独占事業を推進していたのだ。
現在と過去のあいだの対話
数ヶ月たって、僕はこの発見について発表する機会に恵まれた。近世イギリスのエリート男性たちのことを、僕は経験に根ざした女性たちの苦しみと批判に耳を傾けずに国策独占に邁進した「残念な人たち」であるかのように分析してみせた。結果は上出来で、「こういう研究をやる男性研究者が増えたらいいのに」と言われ、自尊心がくすぐられた。研究者の集まりだったので、その時はなぜ僕がこんな研究を始めたのか、説明することはなかった。
しかし、ひとたびYとの衝突と自分の研究テーマを並べて振り返ってみた時、僕は愕然とした。四〇〇年前のロンドンに生きたエリート男性と似たように、僕だって女性の経験を都合のいいように書き換えていたのだ。僕はYが「現実的なところのある」人だから育児制度について調べたのだと思っていたけれど、これは間違いだった。日本で女性が自立して生きようと考えるなら、現実的になって情報収集をせざるをえないのだ。
近世イギリスで新型石鹸を推進しようとした男性たちと、二一世紀の東京で子供がほしいと思った四〇代の男性研究者。まったく異なる文脈に生きる男性としての期待と欲望は、女性の経験に耳を傾けなかったという点では不気味なほど似通っていた。一方は実際の労働に基づく批判を「無秩序」で「口うるさい」ととらえ、他方では愛する女性を「神経質すぎるんじゃない?」と疑った。
いわゆる絶対王政という四〇〇年前の過去は、どうやら認めたくもないほどに過ぎ去ろうとしていないようだ。ジェンダーの視点を持って歴史を振り返るとは、歴史家とその事実のあいだの相互作用の絶え間ないプロセスであり、個人的なことと政治的なことが混ざり合った、現在と過去のあいだの終わりのない対話だったのだ。
PR誌『世界思想』50号は全国の主な書店の無料配布コーナーなどで無料で入手いただけます。送料がかかってしまいますが、弊社から直接お送りすることも可能です。