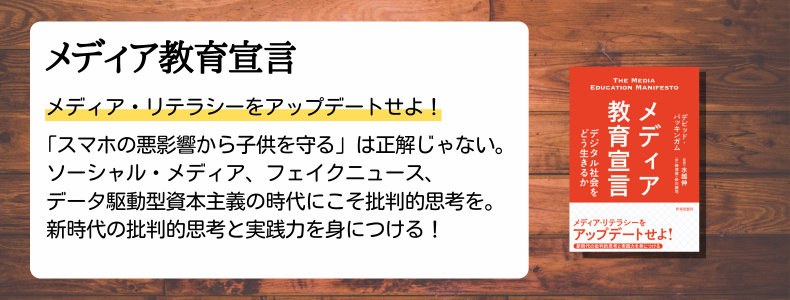『メディア教育宣言』解説+1章
解説 水越伸
『メディア教育宣言 ― デジタル社会をどう生きるか』は、メディア教育の第一人者であるイギリスの研究者デビッド・バッキンガムが2019年に刊行した小さな書物(The Media Education Manifesto)の翻訳である。
原著を出版したポリティ社はリベラルで良質な社会科学系の本を出す出版社であり、バッキンガムもずいぶんたくさんの著書をここから出している。近年、同社はメディア・コミュニケーション研究の領域で「宣言シリーズ(The Manifesto Series)」を出版しはじめた〔中略〕。
批判精神をしっかり持ったメディア・コミュニケーション研究の第一人者に、平明な言葉を使って簡にして要を得た社会的な提言をしてもらうための小冊子。それがこの宣言シリーズのモットーだ。その背景には、危機の時代において研究者は、学問領域にこもってしまうのではなく、社会実践に積極的に介入していく新たな知識人としてあるべきだという考えがある。マルクス、エンゲルスの『共産党宣言』が想起されることはいうまでもない。
メディア教育の領域でそうした宣言書を出す人物として、私はバッキンガムはまことにふさわしいと思う。彼自身はマルクス、エンゲルスにならって、本書の、そしてメディア教育の目的を、「世界をただ解釈するだけではなく、世界を変えることにある」と記している。
バッキンガムは怒っている
本書『メディア教育宣言』において、バッキンガムは怒っている。もちろんその態度は激情に駆られて思いの丈(たけ)を述べるとか、感情のおもむくままに何者かを攻撃するといったものではない。ただこの宣言書の行間からは、2016年の国民投票でイギリスのEU離脱(Brexit)が決まって以降、混乱を極めるイギリス社会にあって、ソーシャル・メディアが台頭する混沌としたメディア状況に取り囲まれつつ、なかなかうまい方策や手立てを打てないで右往左往する行政、学校、ジャーナリズム、大学など、幾重にも折り重なる社会組織のあり方に対する深い怒りの念が感じられるのだ。彼はその怒りを糧にして、関係者を叱咤激励し、今後のメディア環境とメディア教育のあるべき姿を描き出そうと獅子奮迅の論陣を張っている。
バッキンガムの怒りとはなにか。ここでは3つ挙げておこう。
第一に、GAFA(Google, Apple, Facebook, Amazonの略称)に象徴されるプラットフォーム企業の暴力的なグローバル展開と、それに対する国家やEUの無策についてである。
第二に、メディアは害悪をまき散らすものであり、大人はメディアの悪影響から青少年を守らなければならないとする保護主義も、メディア・テクノロジーは人々のコミュニケーションや社会をよくするのだという技術礼賛も、いずれもメディアを複眼的にとらえていない誤った理解であるにもかかわらず、それらがマスメディアやネット空間、専門家を自称する人々のあいだにも相変わらず蔓延している状況についてである。
第三に、メディア教育がそうしたマクロな社会問題とは切り離され、個別教科での教育実践とその評価研究などのミクロな領域に留まりがちな現状についてである。彼は21世紀前半のメディア環境と社会情勢が抱える問題の深刻さを見極めたうえで、今後のメディア教育を考えるにあたってはメディア教育のなかだけで議論をしていては限界があることをはっきり認識している。そしてGAFAやそれに対抗した国家のメディア政策のような外部環境から、ソーシャル・メディアへのアプローチのしかたにいたるまで、幅広いことがらを批判的にとらえて未来に向けた構図を素描しようとしているのだ。
本書の構成
本書の構成は次のようなかたちをとっている。まず現在のメディア環境を概観し、それに関わるメディア・リテラシーの現状と問題点を浮き彫りにする。次にメディア教育を幅広い社会的、学問的文脈のなかに位置づけ、伝統のなかで培われたメディア教育のエッセンスを生かしながら、デジタル・メディア、わけてもソーシャル・メディアに取り組んでいくための立ち位置と道具立てを確かめる。そのうえでソーシャル・メディアをめぐってどのような実践的教育が可能かを例示してみせる。最後に、GAFAなどプラットフォーム企業が台頭する状況に対して国家はどのように取り組むべきかという政策論的な絵図のなかで、メディア教育の今後の可能性と限界を指し示す。
11の小論からなる目次構成は、宣言書として素直で自然な流れを持っている。そのオーソドックスな枠組みが、ともすれば前のめりになりがちなこの種の宣言文にバランスと普遍性を与えているといってよい。
私はところどころ、議論にきめの粗さを感じはした。しかしプラットフォーム企業が幅を利かせ、極端化した政治的意見がソーシャル・メディア上にはびこる現在のメディア環境を鷲づかみにしつつ、他方でメディア・リテラシーの陥った窮状を俯瞰的、かつ建設的に批判できる腕っ節がある人物は、イギリスのメディア教育においてバッキンガムをおいて他にいないのではないか。少なくとも、フェイクニュースやヘイトスピーチの時代にメディア・リテラシーが再び注目されているなどといって嬉々としている「その他一堂」とは、格が違う。痛快さというべきものを、私は読み終えて感じた。〔中略〕
日本のメディア教育の現状
ここで日本のメディア教育の現状を駆け足で論じておこう。1990年代にはテレビを中心とするマスメディアの問題が取り沙汰され、イギリス、カナダなどからメディア・リテラシーという概念が輸入されて議論がさかんになった。その状況は、「マスメディア対インターネット」という構図のなかでメディア環境を論じることができた2000年代半ばまで続いたといってよい。しかしあらゆるものごとがデジタル・プラットフォームに媒介されることが当たり前になるにつれ、マスメディアの弊害といったようなわかりやすい問題点がメディア環境のなかに見出しにくくなり、人々の関心は薄らいでいった。それとともにメディア・リテラシーへの関心、メディア教育への取り組みは停滞することになったといってよい。
この間、小中学校の各教科や高校の教科「情報」などにメディア教育的なものが導入され、ほとんどの大学が共通科目などでメディア・リテラシーを取り扱うようになった。それらをうまく活用する教師は少なくない一方、仏作って魂入れずという結果が多いことも事実である。ちなみに日本では、メディア教育の骨組みとなる国家的なカリキュラムなどは導入されていない。
2010年代半ば以降、スマートフォンとソーシャル・メディアが密接に結びついて発展したネット空間で、ヘイトスピーチ、フェイクニュース、ネット右派をはじめ、極端に片寄った言論がはびこるようになった。イギリスのEU離脱やドナルド・トランプのアメリカ大統領就任などは、そうしたネット空間の存在を抜きには語ることができない。この点についてはバッキンガムが本書の前半で取り上げているが、日本でもほぼそれと同じような問題状況が浮上してきた。それとともに、メディア・リテラシーが再び召還され、注目を集めるようになってきたのである。
2023年現在、こうした状況のなかで、メディア教育、メディア・リテラシーをめぐって、各領域で努力を重ねる人々は存在するが、各領域がうまく連携しておらず、結果として個別に閉じがちで十分な拡がりをみせていないというのが、日本の現状だといわざるを得ない。
〔中略〕
このような問題状況は、少なくとも1990年代にメディア・リテラシーがブームとなった時期からあまり変化していない。私には忸怩たる思いがある。しかし本書を読むと、バッキンガムが私たちに、後ろ向きに嘆くのではなく、前を向いてやるべきことに取り組めと発破をかけてくれているような気がする。最後に日本の状況を打開するための動きを四つ、挙げておこう。
〔中略〕
私たちはバッキンガムからただ教わるのではなく、彼とともに現代的なメディア環境のなかで研究や実践を展開していく必要がある。『メディア教育宣言』はそのことをはっきり示しており、長く読み継がれる古典となるだろう。
*一部抜粋
1章 変化するメディア環境
朝の通勤風景
平日の朝は忙しい。私は都心での会議に向かう途中である。地下鉄は通勤客で混雑していて、みんなそれぞれのプライベートな世界に没頭している。フリーペーパーを読む人もいたが、それはもう車両の床に捨てられている。なかには本を読んでいる人もいるが、ほとんどの人は画面に夢中だ。タブレットや電子書籍を読む人もいれば、スマートフォンでゲームや動画を見る人もいる。多くの人が、電子メール、テキスト、音楽、写真、ツイートをスクロールしている。ほとんどの人はヘッドホンをしている。車両や駅の壁は広告で覆われており、多くの通勤客は、その日着ている服や持っている鞄、デジタル機器を人目にさらすことで、知らぬ間にブランドの宣伝役を担っている。下車して地上へ向かうとき、駅のホームにある大型スクリーン、エスカレーターにある小型スクリーンの前を通過する。それらのスクリーンでは、最新の映画、舞台、展覧会、新譜の発売を宣伝している。駅を出るとすぐに、人々は再びスマートフォンを覗き、地下にいるあいだに逃したメッセージを得ようと熱心だ。
メディアはどこにでもある。まるで空気のようなものだ。推計では、若者たちは今や1週間のうち1日相当の時間をスマートフォンに費やし、少なくとも毎日150回はスマートフォンをチェックしている。モバイル機器、パソコン、タブレット、テレビのことを考えると、10代の若者は1日に約9時間、画面を見つめて過ごしているのだ。さらに、画面を閉じているときでさえ、メディアは、とくに広告やマーケティングのかたちで、私たちの視界に入り込んでくる。そして、私たちはたいてい、これらを疑うことなく受け入れている。コミュニケーションの多くがメディア化されたものであるという事実は、ほとんど注目されないのである。メディアは本当にありふれたものであり、平凡な存在だ。多くの人はメディアから逃れることを望んでいない。あるいは、そういう力を持っていない。
もちろんこうした事例は、モバイル機器、とくにスマートフォンの出現とともにいっそう増えてきた。大画面の前に座っているときだけでなく、私たちは今やいつでもどこでも、さまざまな種類のメディアにアクセスできる。だが同時に、こうした機器は強力な監視手段にもなる。それらは、私たちに関する大量のデータを収集することが可能で、第三者に売ることができる。広告主やマーケティング担当者たちにだけではない。政府や政党、雇用者や就職先、警察やさまざまなセキュリティ企業などに売られるのだ。〔中略〕
利用者としての若者
こうした事態を理解するもうひとつの方法は、個々の利用者の観点からとらえることである。10代とソーシャル・メディア、テクノロジーに関するピュー研究所の年次報告書は、信頼できるひとつの指標を提供している。たとえば2018年には、アメリカでは10代の95%がスマートフォンを所持し、45%が「ほぼ常に」ネット上にいると報告している。さまざまなサービスの人気は年々変化しており、フェイスブックの人気は下降傾向にある。フェイスブックを定期的に利用していると答えた人は、半数に過ぎない。それに比べ、ユーチューブを利用している人は85%、インスタグラム(Instagram)やスナップチャット(Snapchat)を利用している人は約70%である。イギリスのメディア規制機関であるオフコムが実施した年次調査からも同様のことが明らかになっているが、その調査では「旧来の」メディアにも焦点があわせられている。2017年には、12~15歳の95%が週平均21時間、インターネットを使っていた。91%が週平均15時間テレビを見ており、83%が自分のスマートフォンを持っていた。この調査では、とくに年齢の高い子どもにおいて、テレビ放送から(タブレットを含む)もっと新しい機器やユーチューブへの移行が続いていることが確認された。ここでもスナップチャットのような新たなソーシャル・メディアが徐々にフェイスブックに食い込んできている。もちろん、年齢、社会階級、性別による違いはあるが、おおむね、今日の若者たちが、睡眠も含めた他のどのような活動よりも、メディアとの関わりに多くの時間を費やしていることは明らかだ。
プラットフォーム企業
そしてこの事態を検討する第3の方法は、これらのデジタル・サービスやプラットフォームを所有し、提供する企業の側からとらえることである。そこでわかるのは、たった4つの主要企業のあいだで、独占に向かう急速な成長の傾向があるということだ。〔中略〕
GAFA(ガーファ)と呼ばれることもあるグーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンの4社は、それぞれに異なる歴史、市場イメージ、企業戦略を持っているが、いずれも過去10年ほどで驚異的なスピードで成長してきた。ここにマイクロソフト(Microsoft)やIBMなどの有名企業や、ネットフリックスやツイッターなどの新興企業を加えれば、デジタル技術やサービスの世界市場のほとんどすべてを網羅することができる。これらは世界で最も収益性の高い企業であり、その収益を維持しようといそしんでいる。
私はあとでこれらの問題に立ち返るつもりだが、ポイントは、これらの企業がたんなるテクノロジー企業ではなく、メディア企業でもあるということだ。インターネットを通じて、とりわけデジタルなプラットフォームやサービスを介して、私たちはますます、あらゆる種類のメディアにアクセスするようになっている。これらの企業は、たんにテクノロジーとしてのハードウェアやソフトウェアを提供しているだけではなく、現代生活に欠かせない表現やコミュニケーションの手段もどんどん提供している。かつてレイモンド・ウィリアムズは、テレビとはたんなるテクノロジーではなく、意味や快楽をもたらす文化的形態でもあると言った。同じように、フェイスブックやツイッター、インスタグラムのようなサービスは、たんなるコンテンツの配信手段ではない。コンテンツ、およびコンテンツと私たちとの関わりを独特の方法で枠づける、ひとつの文化的形態でもあるのだ。
基礎的な権利としてのメディア教育
すでにおわかりかもしれないが、私たちはメディアをいくつかのレベルで理解する必要がある。利用者の観点からは、これらのメディアをコミュニケーションや娯楽、学習などに用いられるサービスや製品としてとらえることができる。しかし、すでに示したように、制作者や所有者の側から、商業的利益を生み出すサービスや製品としてもとらえる必要がある。私たちはいくつもの実践―利用者と制作者がなにをしているのか、どのように、そしてなぜそのようにしているのか―を検討する必要があるのだ。また、利用者と制作者が生産し、シェアし、消費している実際のコンテンツも検討する必要がある。現在のメディア状況には、誰もが関わっている。メディアを理解するとは、もはや「マス」メディアや大企業の生産物のことだけではなく、私たち個々人がなにを作ったり制作しているのか、コミュニケーションのためにどのようにメディアを用いているのかを理解することでもあるのだ。〔中略〕
この宣言書は、現代において市民であるための根本的な必要条件としての、ひいてはあらゆる教育システムにおける基礎的な権利としての、メディア教育のあり方を示すものだ。ただし同時に、私独自のメディア教育のとらえ方を主張してもいる。すなわち、メディア教育は、メディアやテクノロジーを、教具や教材、データ収集のための機器として使う営みではない。メディアが若者たちに促すさまざまな「悪いおこない」を警告することでもない。たんに技能を発達させたり、自己表現の機会を与えたりすることでもない。私が提唱するメディア教育は、おもに、批判的理解を発達させる営みに関わるものなのである。
*一部抜粋、原注・訳注は省略、小見出しは追加。
目次
日本語版刊行に際して
序
1 変化するメディア環境
2 利害を超えて
3 メディア・リテラシーの限界
4 より大きな構図
5 批判的にいこう
6 いかに教えるべきか――落とし穴と原則
7 ソーシャル・メディアを概念化する
8 メディア教育の実践
9 実現できること
結び
原注
訳注
解説 水越伸