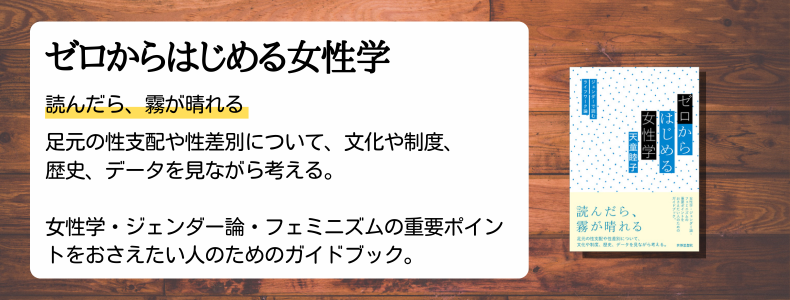『ゼロからはじめる女性学』まえがき
早春のある日、卒業間近の学生が「大学で女性学やジェンダーを学べてよかったです」と伝えに来てくれました。女性の生き方を問うライフワーク論やキャリア形成科目は、女子大学ならではの教育の事例です。そして学生のみなさんとの語り合いは、自らが歩んできた学びの過程を思い起こすときでもありました。
「女性学」との出会いは、私の人生にとって大きな転機でした。ずいぶん前のことですが、一九九〇年代、三〇歳代の私は出口の見えないトンネルの中にいるような閉塞感を抱いていました。子どもはかわいいが、ときに育児は思うようにいかず、再就職の壁は厚く、自分の人生はどこに向かうのか、道を見出せずにいました。従妹の結婚式で偶然出会った教授に「母校(の女子大学)に社会学専攻の大学院ができますよ」と声をかけられ、一念発起して受験勉強し、昔の恩師に電話して読むべき本を尋ねました。社会人入試の枠はなく、語学も一般受験で、たまにやっていた翻訳の仕事の経験が思わぬところで役立ちました。
大学院で「ジェンダー」ということばに出会い、その視点で世の中を見渡すと、自分が社会に出てから経験した苦い思いや子育て期の孤立、背景にある性別役割分業型社会のからくりが見えて、一気に霧が晴れる思いでした。学ぶことは生き直すことでした。
その後、運よく大学に職を得て、いくつかの大学で女性学、ジェンダー論、教育社会学を教えてきました。私は仙台生まれで、二〇一五年に宮城学院女子大学の女性学担当教員として赴任しましたが、故郷に戻ったきっかけは東日本大震災でした。すでに震災から年月が経過していたものの、ひとたび津波の被災地を訪れると、被災前の生活環境を喪失したままの地域の姿があり、胸が痛みました。家族関係や子育てにも厳しい現実が見えました。研究者として何かできるはずとの思いが、私をあらためて女性学教育に向かわせました。
女性学に何ができるか。学生のみなさんと接しながら得た答えの一つは、困難にあって足元の課題に向き合う内なる力、連帯の力を生み出す学問と実践、それが女性学の強みだということです。とりわけ学生たちのまなざしが真剣さを増すのは、性支配や社会に構造化された性差別が遠い過去の話ではなく、今なお身近に存在することに自ら気づくときです。「(医科大学の)入試の性差別に愕然とした」「就活が不安」「将来が想像できない」といった彼女たちの本音はやがて「女性の生き方の変化を学び、祖母世代の苦労が理解できた」「国際比較のデータで日本の現状を知り、自分に何ができるか考えようと思った」「震災時は小学生だった。女性学を学んでいつか支援や復興の担い手になりたい」といったことばへと変わっていきます。ときに思うようにいかず心が沈み込むときがあっても、学びを通して、光を見出し、理不尽な状況には自ら「声」を上げてよいのだと知っていくのです。
本書は、女性学・ジェンダー論的アプローチで、八つの章から構成されています。主に近代以降の社会変化をたどり、歴史的視点という縦軸と国際比較の横軸を交叉させて、人生の諸課題に接近していきます。
序章では本書の鍵となるライフワークの意味、生産と再生産、ケア、ウェルビーイング、女性のエンパワーメントといった用語を解説し、日本の女性のライフコースの変化を見ます。第1章ではフェミニズムの歴史と展開を学び、女性学やジェンダー概念がどのように生まれたかを把握します。第2章では国際比較の視点から、労働、生活時間の現状を読み解きます。第3章では身体と性の自己決定にかかわる「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」、第4章では日本の家族と子育ての変化、第5章では学校教育における「隠れたカリキュラム」など、教育やスポーツ文化に潜む性差別を取り上げます。第6章では地域女性のエンパワーメント、災害女性学を紹介します。そして終章で女性の就労、育児、教育、ケアといった課題を包括的にとらえる「エンパワーメント・モデル」を提起します。各章の末尾に、「知っておきたいキーワード」と読書案内があります。「考えてみよう」の問いも自由に役立ててください。
女性学を初めて学ぶ人のために、ジェンダー論を応用したい人のために、また人生を重ねていくうえでライフワークを広く考える書として、本書が活かされることを願います。
これまで声を上げにくかった女性、男性、マイノリティの人々を含め、よりよく生きるために、ジェンダー平等の社会課題をともに考えていきましょう。
挑戦は変化の種です。本書があなたの未来をひらく扉となれば幸いです。
目次
まえがき
序 章 女性学で読み解くライフとワーク
1 女性学的想像力でひらく未来社会
2 ライフワークを読み解く鍵
3 女性の生き方はどう変わったか
4 よりよく生きるために──グローバル・ローカルな視点
第1章 越境するフェミニズム
1 フェミニズムの歴史と展開
2 第二波フェミニズム──ジェンダー、女性学の誕生
3 第三の潮流──フェミニズムの多様性
第2章 働くこととジェンダー
1 女性の活躍とワーク・ライフ・バランス
2 ジェンダー化された労働
3 生活時間の国際比較
4 働き方とジェンダー平等──ジェンダー格差を超えて
第3章 性と身体の自己決定
1 再生産とフェミニズム
2 日本の妊娠・出産をめぐる政策変容
3 リプロダクティブ・ヘルス/ライツと性的自己決定権
4 少子化対策はだれのためか
第4章 子育てはどう変わったか
1 育児戦略で読み解く家族と子育て
2 子育ての社会史──江戸から明治・大正期へ
3 近代家族と子ども中心主義──高度経済成長期以降の子育て
第5章 教育・スポーツ文化をジェンダーで問い直す
1 文化伝達と「隠れたカリキュラム」
2 教育におけるジェンダー平等の取り組み
3 スポーツ、ジェンダー、性の境界
第6章 地域女性とシティズンシップ
1 女性と地域社会
2 災害女性学をつくる
3 農業と男女共同参画
4 SDGsと女性──地域から変える、変わる
終 章 女性学でひらくエンパワーメント
1 ローカルとグローバルをつなぐ
2 女性の自立とエンパワーメント
3 構造的不平等への挑戦
4 困難からエンパワーメントへ
参考文献/索引
*各章末に「考えてみよう」「知っておきたいキーワード」「さらに学ぶための本」付き