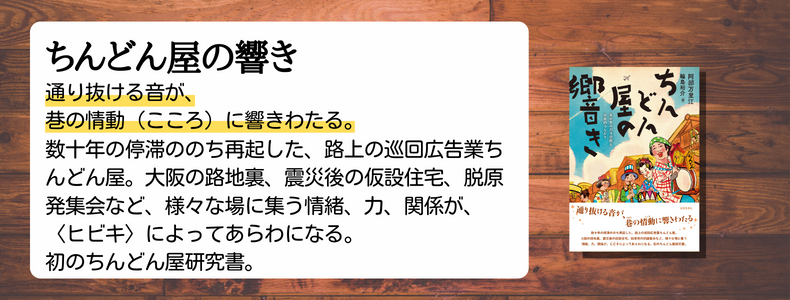プロローグ 『ちんどん屋の響き』より
通り抜ける音が、巷の心に響きわたる。大阪の路地裏、仮設住宅、脱原発集会などで再起した、路上の巡回広告業ちんどん屋。初の研究書。
阿部万里江著/輪島裕介訳『ちんどん屋の響き――音が生み出す空間と社会的つながり』より、プロローグ「始まり」を紹介します。
一
二〇一五年、大阪の住宅街の静かな通り。風変わりに着飾った四人の楽士たちがそぞろ歩いている。オレンジがかった茶色の着物に明るい色の帯を締め、時代劇風のカツラとメイクを施したクラリネット奏者が一九七〇年代のヒット曲を吹いている。同じく派手な着物とカツラの二人の打楽器奏者が続き、一人は肩から斜めに吊るした大太鼓、もう一人は木の枠に据え付けた様々な和楽器の鳴り物を鳴らして旋律に合いの手を入れる。四人目は慎重な、しかしユーモラスな足取りで通りをジグザグに歩き、笑みをたたえて通行人に近づいては、近所の肉屋の大売出しチラシを手渡す。彼らはちんどん屋。日本特有の巡回広告楽隊だ。
ちんどん屋は、音楽活動とも、商売とも、単なる日常の背景音ともみなされている。その音は遠くまで聞こえる。三階のバルコニーの窓からおさげの女の子が、あの音はどこからくるんだろう、と知りたげに顔を出している。ぼさぼさ頭のおじいさんが、下着姿なのもお構いなしでちんどん屋を見に家から出てきた。エプロン姿でサンダル履きのおばちゃんたちが、今日は何の宣伝かとしゃべり合っている。近くの歩道を歩いていたおばあちゃんは、ぼんやりと懐かしげに眺めている。その横をサラリーマンが何人か慌ただしく歩き去っていく。ちんどん屋の音が鳴り響くところ、どこへ行っても、その後には活気ある社会的つながりがあらわれる。私の親の世代にとってちんどん屋は、第二次世界大戦後の日常的な音風景の一部だった。彼らの派手で突飛な存在は、非日常的であると同時に当たり前な生活の一部でもあった。この世代の人たちからは、ちんどん屋の音に魅了された子どもたちがずっと後をついて行って迷子になってしまったという、おとぎ話の「ハーメルンの笛吹き」めいた話をしばしば聞くことがある。ちんどん屋はどこか違ったところがある。どこか魔術的で、空想的で、どこにでも出現するのにいつでも「場違い」な存在のようだ。
私の世代は違う。一九八〇年代に東京で育った私には、ちんどん屋を身近に見聞きした記憶はない。しかし、学校で友達と「ばーか、あーほ、ちんどん屋」と互いに囃し立てていたのは覚えている。当時はなぜ音を使った広告業の名前があざけりの文句に使われるのだろう、なんて考えもしなかった。ただ、それはある種の違いを示しているのだ、とだけ漠然と感じていた。でも、その「違い」とは一体何なんだろうか?
商店街の真ん中を歩くちんどん通信社(著者撮影)
二
二〇〇四年のうだるような暑さの日、下北沢のお気に入りのジャズ喫茶に座っていた私の耳は釘付けになった。店主は古典的なバーテンダー風の衣装に身を包み、気難しそうだが実はとても注意深く、さりげなく気を配ってくれる。彼は、いくつかのアルバムを続けてかけた。ディキシーランド・ジャズ、沖縄民謡、バルカン風プログレと、それぞれ全く違うスタイルながら、共通する音が鳴っていた。ちんどん太鼓だ。それ以来、私は惹きつけられ、その音の糸を辿っていくことになる。その後一〇年以上続く旅の始まりだった。
ちんどん屋の音を追いかける中で、私は思ってもいなかったいろいろな場面に誘われた。東京の小さなナイトクラブで、シカラムータというバンドが活気に満ちた不協和音を炸裂させている。クラリネットはクレズマーのような旋律をいななくように奏で、チューバ、ドラムス、アコーディオンは、バルカン音楽を思わせる跛行するような複雑な変拍子を刻んでいる。そして、その中をちんどん屋を想起させる和楽器の鳴り物各種が鳴り響いている。
本州から南に遠く離れた沖縄本島のレコーディングスタジオで、伝統的な民謡歌手、大工哲弘がアメリカ占領に反対する古いプロテストソングを歌っている。その曲は東京のミュージシャンたちによって編曲・伴奏されており、二人の女性奏者がちんどん太鼓でリズムを彩っている。
一九九五年の阪神・淡路大震災と二〇一一年の東日本大震災の後、ちんどん屋の音は、瓦礫と仮設住宅の中で鳴り響いていた。生き残ったものの仮設住宅に引きこもりがちな被災者たちに訴えかけようと、ちんどん屋の音と記憶を喚起するような様々な種類の生音の楽器を手にした。
東京の中心部、首相官邸前でちんどん太鼓の甲高い鉦の音が太鼓の轟音を突き抜けて響いている。二〇一一年の東日本大震災と福島第一原子力発電所の爆発事故後、日本各地で行われた原発再稼働に反対する抗議デモだ。
このように、もともとの広告という文脈を超えて、ちんどん屋の音は多くの聴き手と文脈の中で共鳴しているようだ。ちんどん屋の音の社会的な力は波紋のように広がり、予想外の回折的(diffractive)な形を生み出す。このように様々な場に現れるちんどん屋という特殊な実践の、一体何がかくも幅広い音楽的な表現を生み出しているのだろうか? ちんどん屋を参照することによって、これらの音楽家たちはどのような文化的はたらきをなしているのだろうか?
 2012年、東京での脱原発デモに参加するジンタらムータのメンバー(デイヴィッド・ノヴァック撮影)
2012年、東京での脱原発デモに参加するジンタらムータのメンバー(デイヴィッド・ノヴァック撮影)
三
トロブリアンド諸島に上陸した有名な文化人類学者マリノフスキーではなくとも、フィールドワークはしばしば孤独な仕事だ。私は自分の生まれ育った場所に戻って研究をすることになったのだが、故郷にいるにもかかわらず、あるいはだからこそ、さらなる疎外感を感じることになる。フィールドワークのために大阪に着いた当初、わけあってしばらくインターネットカフェの小さな個室で夜を過ごした。そこで、不安定な雇用で賃貸住宅に定住できずネットカフェに泊まり込む「ネットカフェ難民」の日常を目の当たりにした。孤絶の感覚がひしひしと伝わり、現代のポスト工業社会のグローバル都市において、孤独とは社会の病である、という診断を裏書きしているようだった。『ガーディアン』紙の記者、ジョージ・モンビオット(Monbiot 2014)は、われわれの時代を孤独の時代と名づけ、新自由主義経済モデルを規定する個人主義と競争原理がわれわれの社会の社会的・道徳的な構造を切り崩す、「断絶の倫理」がその特徴であると指摘している(Gershon and Alexy 2011)。
青信号のたびに三〇〇〇人(一日五〇万人)もの人が行き交う渋谷のスクランブル交差点に行ったことがなくても、群衆の中の孤独という逆説的な感情を経験したことがあるだろう。人混みに揉まれる中で、われわれは自分が孤独な存在であることを強く自覚するようになる。人口過密な都市の公共空間での社会的疎外の感覚は、グローバルな大都市ではごくありふれた経験だ。この交差点は、グローバル資本とテクノカルチャー産業の循環によって駆動された日本の高度な消費主義のアイコンとなっている。そこにはデジタルの音と映像が溢れかえっている。新作映画やテレビドラマやポップ音楽のアルバムの宣伝の合間に、人材派遣会社や賃貸住宅会社の広告が挿入される、巨大なLEDスクリーン。チェーンのレストランや居酒屋の明滅するネオンサイン。数えきれないほどの街頭宣伝スピーカー。これらはけたたましくぎらついた新自由主義的資本主義の標徴であり、それは麻痺的な都会の孤独の感覚をさらに強める。この過剰な感覚的刺激に囲まれて、ほとんどの歩行者は原子のように細分化されている。誰もぶつからずに歩いているのは奇跡だ。歩行者たちは速く確かな足取りで混雑した交差点を注意深く通り抜け、他人の間の空間をジグザグに横切り、しかも接触を避ける。まるで社会化された都会の振り付けを踊っているかのようだ。この交差点が、映画『ロスト・イン・トランスレーション』の登場人物の、無感情と孤独の背景となったのは、実につきづきしいと思える。
ある日、私はこの交差点を歩いていた。心身ともにかなり弱っていたときだったこともあり、至るところに氾濫する消費主義の感覚的標徴に圧倒され、すでに経験していた孤独の感覚がさらにはっきりと浮き彫りになった。そんな中、突然、交差点を横切ってそれぞれの道を歩く人の波の中で、大阪でインタビューをしたちんどん屋の林幸治郎の言葉がよみがえってきた。「家の中にいる人に聞かせているのよ。……街中ハッピーな人はいないよ。あんまりね。……鬱の人が[家から]出てくるような音を[出さなきゃいけない]」。インタビューのときは、その発言はなんだか悲観的なように聞こえた。もしかして、自分自身の苦難を大阪都市部の見えない聴衆に投影しているのではないかとさえ思った。でも、そのとき、交差点の途中で、私は突然、林と同じように世界が聞こえたのだ。この群衆の中で孤独の重さを感じていたのは私だけではないだろう。ちんどん屋の実践者がどのように社会関係やその断絶を「聞いている」のか、私はそのとき理解した。この知覚の変化によって、私は孤独感から引っ張り出された。個人的疎外感は、実は集団的な社会状況である、ということが突然わかったのだ。私のフィールドワークの中で、これは最も深遠な瞬間の一つだった。このとき初めて私は、ちんどん屋の音の労働は、ある社会的つながりに関する哲学に深く根ざしているということに気づいたのだ(ここでは「社会的つながり sociality」を、人々が必然的に他人や周りの環境と関わり合うダイナミックな過程と理解する)。
*
ちんどん屋、すなわち雇い主の商売を宣伝するために雇われた、派手に着飾った大道の楽士の集団の起源は一八〇〇年代半ばまで遡れる。その最盛期の一九五〇年代には、ちんどん屋はどこにでもいて、日常の音風景や、「大衆」という観念や、近所の小さな道端での活き活きとした社交、といったものと深く結びついていた。しかし、一九六〇年代になると、ちんどん屋は急激に衰退する。彼らは冗談の種や懐旧の的になったり、怪しげで迷惑な存在とみなされるようになる。無関心に扱われるのが関の山だ。しかし、数十年の停滞ののち、現在では、一九九〇年代初頭に始まる再起の途上にある。時代錯誤や曖昧模糊とレッテルを貼られながらも、いくつかのちんどん屋集団はそれなりの経済的成功を収め、ちんどん屋の感性はロックやジャズや実験音楽のミュージシャンに取り入れられて、異種混淆的な音楽実践へと変貌している。大阪の商店街や路地裏で、京都の在日コリアンが多く住む地区の夏祭りの踊りの場で、国際的に流通する「日本の音楽」のコンピレーションCDで、そして三・一一後の東京での脱原発抗議集会で、といったように、今日、ちんどん屋の音楽は、さまざまな場所、歴史関係、音楽様式、商業活動、政治的志向が交差する地点で鳴り響いている。
本書は、それらの交差点で響くちんどん屋の音から私が聞き取ったものから生まれている。ちんどん屋の実演とそこから派生した様々な音楽実践に随伴し、自分も演奏する中で、私はちんどん屋の音が都市の隣近所に音響として鳴り渡るだけでなく、それらの音が様々に異なる文化的な働きをなすのを聞いてきた。ここでいう音のなす働きとは、過去を想起させ、様々な感情的反応を呼び起こし、人々が予期せぬ出来事や場所や音との関わりを創り出すよう触発し、国家の構造的な暴力に抗議するなどといったことだ。九年以上のフィールドワークの中で、私は、ちんどん屋が現代日本の都市風景の中で生み出す社会的、歴史的、政治的、情動的な響きに魅了されるようになった。ちんどん屋は、都市の社会的つながりの情動的相互関係に対応するため、特別な聴覚的感性とパフォーマンスの方策を養う。この感受性と戦略こそが、彼らの生業なのだ。つまり、情動と音響を通じて社会的つながりを創り出すことこそが、ちんどん屋の仕事なのである。ちんどん屋は、その事業が情動を生み出すことと密接に結びつく業態であるため、音と、公共空間と、社会関係によって形作られる公的な親密性の感覚が、どのように関係しているかを考察するためのきわめて魅力的な事例である。彼らの仕事が作り出そうとする音のアフォーダンス(環境が生み出す能力)に注目することで、公共空間をいかに理解しうるのか、そして、ちんどん屋の音が響く都市空間においていかなる社会的結合と断絶が生起しているのか、ということを考察していきたい。
〔中略〕
ちんどん屋の歴史的・文化的特殊性に対して、ヒビキという分析レンズを用いて民族誌的な関心を向けることで、些末にも時代錯誤的にも非政治的にも思われがちな実践の中で、次のような実に多様な働きが演じられているのが聞こえてくる。たとえば、ちんどん屋の響きは、社会的周縁化の様々な歴史を明らかにし結集させることによって、日本が均質な国家だという通念に挑戦する。その響きは、様々な資本の歴史が、現在において同時に存在することを示し、いわゆる西洋的な資本の語りを複雑化する。その響きはまた、社会的つながりというものを相関的に理解すべきであることを強調し、自由主義特有の主体の観念を動揺させる。さらにその響きは、これまで日本の街頭抗議の政治的可能性を閉ざしてきた絶対空間的な公共空間の理解を突き崩していく。ちんどん屋がその音によって聞く人を魅了するように、私はこの本が、音―空間の多くの批判的な響きについて読者に熟考を促すものであってほしいと願っている。その響きは、私たちが住む社会的世界の多様な歴史、政治的可能性、相関性に、私たち自身が深く耳を傾け、調律することへと誘っている。
目次
推薦の辞――林幸治郎/大熊ワタル
日本語版への謝辞――阿部万里江
プロローグ 始まり
序章 ちんどん屋の響き
1 音の哲学者であり路上の民族誌家としてのちんどん屋
2 ちんどん屋の音と歴史
3 今日のちんどん屋
4 ちんどん屋の曖昧さ
5 本書一連の問い
6 ヒビキ/響き
7 方法についての覚書
8 章立て
第1章 歩く歴史
1 身体化されたヘテロフォニー
2 歩く技術
3 街のリズム――街の歩行者を歴史化する
第2章 魅惑を上演する
1 民族誌的おとぎ話
2 ちんどん屋、他者性、同質性
3 大衆を歴史化する
4 懐かしさ、無垢、差異
第3章 想像共感の音を出す
1 移り行く近代性の地理――街路、公共空間、社会的つながり
2 音の商売と想像共感
3 町廻り――都市空間を交渉する
4 ヒビキ――情動の響きと音響の響き
5 ちんどん屋を雇う――「賑やかさ」
6 反個人主義の美学
7 即興について
8 洗練された不器用さ
9 聞き流されるために雇われる
10 響きと公共的親密性
11 ちんどん屋の不安定な聴衆
第4章 ちんどん屋を政治化する
1 ちんどんに触発されたプロジェクト
2 公共空間の危機
3 情動的類似性を探り当てる
4 まつりごと――祝祭性の政治
第5章 沈黙の響き
1 街頭抗議におけるちんどん屋
2 ちんどん屋の音の労働――情動的かつ音響的な響き
3 自粛の沈黙
4 生存の政治を音にする
5 賑やかさと生存の倫理
エピローグ 響きのアフォーダンス
付録
注
解説 響け、ちんどん世界――細川周平
訳者あとがき
参考文献
索引