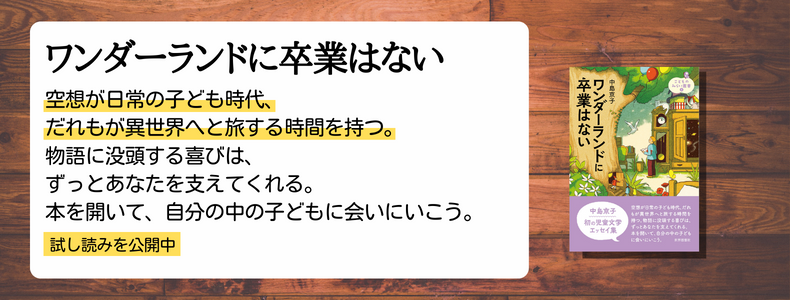物語に没頭する、圧倒的な幸福感――ロバート・ルイス・スティーヴンソン『宝島』
空想が日常の子ども時代、だれもが異世界へと旅する時間を持つ。
物語に没頭する喜びは、ずっとあなたを支えてくれる。本を開いて、自分の中の子どもに会いにいこう。
『クマのプーさん』から『ゲド戦記』まで――作家を育てた18の物語。
直木賞作家・中島京子による初の児童文学エッセイ、『ワンダーランドに卒業はない』より、「物語に没頭する、圧倒的な幸福感――ロバート・ルイス・スティーヴンソン『宝島』」を紹介します。
おもしろい児童文学には法則がある。
作家が親しい子どものために書いたものは、外さない。例はいくつもある。
第1章に紹介した『クマのプーさん』は、ミルンが息子のクリストファー・ロビンのために書いたものだし、『不思議の国のアリス』は、ルイス・キャロルことドジソン先生がリデル家の娘のために作ったお話だ。ジェイムズ・マシュー・バリーは、親しくしていたデイヴィス家の子どもたちにインスパイアされて『ピーター・パン』の物語を作り上げた。どれもこれも、児童文学の金字塔的な作品だ。
そして、『宝島』も、小さな少年の聞き手のためにつむがれて、やがて世界中で読まれることになった、児童文学の傑作中の傑作であることは間違いない。
ロバート・ルイス・スティーヴンソンは、十歳年上の妻ファニー・オズボーンの連れ子であるロイド少年のために、一枚の地図を書いた。「宝島」と名づけたその地図は、作家の想像力をおおいに刺激して、彼はロイド少年のために、ジム・ホーキンスという少年が主人公の冒険小説を、せっせと語り聞かせることになる。
興味深いのは、あまりに物語がおもしろかったので、聞き手が少年だけではなくなってきて、とうとうスティーヴンソンのお父さんまでが、ジムが宝島の地図を見つけることになる船員衣装箱の中身を考えて、あれが入ってるんじゃないか、これを入れたらいいと、アドバイスしていたという話だ。そう、一人の少年のために作られた物語だけれど、最初から幅広い年齢層の熱狂的な読者を得ていたのは、『宝島』という小説の性格を表してあまりあるエピソードだという気がする。
初めて読んだのは、中学生のころだ。
手元に、そのときに読んだ文庫本があるので、ボロボロになっているその本を、今回、また読み直すことになった。
といっても、『宝島』を読み直すのは、ものすごく久しぶりのことだった。
たぶん、三十年以上は経っているんじゃないかと思う。
ほかの作品と違って、手に取るのが久々だった理由はなんだったんだろう。何度も読んだ作品は、もう少しちまちました、日常の延長にあるような冒険なり、エピソードがあるものだった気がする。『宝島』は、スケールが大きいので、読み終わるとほんとに長い旅をしたような心地になって、すぐまた同じ旅に出かける気にならなかったんじゃないか。
ジム・ホーキンス自身、同じ旅に出ようなんて、まったく思わなかっただろうし。
でも、『宝島』を読むときの、あるいは読み終えたときの幸福感は、ちょっとほかでは味わえないような体験だった。おもしろくておもしろくて、続きが読みたくて読みたくて、ほんとに一気に読んでしまう。読んでいる間、ずっとその楽しさが続く。最後の最後まで、どうなるのか、続きはどうなるのかとハラハラさせられる。
小説のおもしろさを、これでもかと詰め込んであるのが『宝島』で、そう、物語そのもの、物語ることのおもしろさを教えてくれたのが、この本だった。
久々に読み返すことのメリットは、細部をすっかり忘れていることだ。
まんまと、初読のときとおんなじ体験をした。いわゆる一気読みというやつで、ベッドに入って本を開き、睡魔で本を手放さなければならないのがなんとも悔しい。
これくらい幸福な読書は、そうはない。
「ベンボー提督屋」という旅館に、一人の男がやってくる。
「死人の箱にゃあ十五人――
よいこらさあ、それからラムが一瓶と」
なんだか不気味な歌を歌うこの男はジム少年にコインを渡し、
「一本脚の船乗りを油断なく見張れ」
と頼む。
大きな船員衣装箱を持っているこの大酒飲みは、たえずラムを飲んで酔っ払っている。ある日、また別の男(この人には両脚があるのだが)が訪ねてきて、彼らがどうも海賊の残党であるらしいことが明かされる。大酒飲みの男は、昔の海賊仲間が彼の宝物を狙って行動を起こしたことを知ったその日に、長年の不摂生がたたって死んでしまう。船員衣装箱が残される。海賊仲間たちはそれを目的に「ベンボー提督屋」に押しかけるが、その前に危機一髪、ジム少年と母親は、衣装箱からいくばくかのお金と、油紙に包まれた一枚の地図を手に入れることに成功する。
一枚の地図。そう、宝島の地図だ。
そうして海の冒険が始まる。完璧なスタート、最初の最初から、読者をぐいぐいと物語に吸い込んでいく、この吸引力といったら!
一つだけ、ちょっと都合がいいのではないかと思うのは、主人公のジム・ホーキンスがかっこよすぎることかもしれない。この子はスーパーヒーローで、子どもなのに、なんでもできる。誰の指図も受けずに、自分一人の意思で行動して、それがじつにうまく運ぶし、何度も味方の危機を救う。
でも、じつの話、それがなんともいえない読み心地のよさを保証しているとも言える。
この物語は、ジム・ホーキンスが冒険を振り返って語る回想形式で書かれているので、ジムが無鉄砲な冒険に踏み出すときによく、それがのちにどういう結果を生んだかを、あらかじめ話してしまうのだ。これはちょっと、「ネタバレ」的な手法なのだけれど、ものすごい危険に乗り出す少年を、しかしきっと彼は失敗しないし、味方にとっていいことが起こるのだと信じて、読者が彼を冒険に送り出す余裕を持てるので、そのあたりが子ども向きというか、怖くなさを保証してくれるところでもあると思う。
たとえば、初めて彼がコックのジョン・シルヴァー(世紀の悪役で、こんな魅力的な人物はなかなかいないと思われる)が裏切り者だと知る場面では、ジムは林檎のいっぱい入った樽に隠れて、ジョン・シルヴァーたちの悪巧みを盗み聞きすることになるのだが、「しかし、いずれわかるように、よいことがこの林檎樽から起こったのだ」と、林檎樽の冒険が始まる前に、作者は、そしてジムは、まず読み手を安心させておく。もしかしたら、ロイド少年が怖がりすぎないように、予防線を張りつつ進んだのだろうかと、想像してしまう。
だって実際には、林檎樽に隠れて聞く話はものすごくおそろしいのだし、ジムは一歩間違えばこのときに殺されていたかもしれない。もちろん、主人公を小説の六分の一しか進んでいない場面で殺すようなことはしないと、大人なら誰でもわかるけれども。
ともあれ、そうした危険を、ジム少年はこれでもかこれでもかとくぐり抜けることになる。正当防衛とはいえ、悪い海賊をピストルで撃つ事態も起こる。ジムの活躍は半端ない。
主人公が無敵すぎるところは、多少、スーパーヒーローものらしい偏りはあるけれど、それを感じさせないほど、ジム少年は魅力的だし、それになんといっても、ジョン・シルヴァーがこの物語のもう一人の主人公であることを、疑う人はいないだろう。
この児童文学が世に出たとき、ジョン・シルヴァーが悪すぎるという批判があったそうだ! 子どもの小説なのに、悪党が改心もしなければ罰せられもせず、悪の限りを尽くしておいて逃げ果せるなんて、いかんではないか、と。
そして、『宝島』が『宝島』たるゆえん、この作品がもう、最高に、ずば抜けて、おもしろくてしょうがないのは、どう考えてもジョン・シルヴァーのおかげなのだ。この人がちょっとでも改心したりしたら、作品は台なしになっちゃうではないですか!
ジョン・シルヴァーは、とても人当たりのいいコックとして登場する。だいたい、この本のタイトル自体、初めは「船のコック」だったんだそうだ。作者にとって、相当思い入れのある人物に違いない。
誰もが彼に騙される。ジムももちろん騙されるし、最初は感じの悪いいけすかない人物として登場し、のちに一人だけ物が見えていた人ということがわかるスモレット船長すら、ジョン・シルヴァーにだけは騙される。だって、彼は一本脚というハンディキャップがあり、自分を「爺さん」と呼んだりする年齢でもあって、屈強な海賊の悪役然としていないのだ。しかも物腰の柔らかい、楽しいコックで、なにかやらかしそうなそぶりなんかぜんぜん見せない。でも、彼には裏の顔がある。裏の顔があるが、するりと表の顔をつけることもある。変わり身が早くて、絶体絶命の事態に追い込まれても、必ずなにかをつかんで逃げ果せる。『宝島』以後、悪役といえば、彼の影響を受けて造形されているのではないかと思われるほど、かっこいい。
最初から、ジョン・シルヴァーはジム・ホーキンスを買っていて、それはもちろん、そうするのが有利だと判断するからだ。でも、それだけじゃないような気がする。二人はちょっと似ている。ものすごく頭がいいところと、状況をみて、人に相談したり頼ったりせず、自分の意思だけで意表を突く行動に出るところが。
妙な想像だけれど、ジョン・シルヴァーの少年時代はジム・ホーキンスみたいだったんじゃないかと思わせるようなところがある。
それから、スティーヴンソンといえば『ジキル博士とハイド氏』を書いた作家だから、この大ヒット作にして処女作である『宝島』に、ものすごい二面性を持つジョン・シルヴァーという人物を登場させたことと、もう一つの代表作には、どこかつながりがあるのかもしれない。
ともあれ、『宝島』のすごさは、まったく、どこにも、説教臭さが存在しないことだ。ジムはかっこいいけど、お行儀のいい子なんかではまったくないし、読者はみんな悪役のジョン・シルヴァーに惹かれてしまう。
『宝島』から、よい子のための教訓を得ようというのは不可能だ。
けれども、こうして紹介しているわたしを育ててくれた本の中で、ともかく一冊、一冊だけ、誰にでもオススメするのを選べという過酷な条件が突きつけられたら、わたしはたぶん『宝島』を選ぶ。
こんなにおもしろい小説はない。こんなに幸福な読書を約束してくれる本はない。
もし、手に取って、ちょっと難しいと思ったら、楽しめるようになるまでほっといたっていいと思う。訳文もいくつか出ているので、ぜひ、読みやすいのを探していただきたい。だけど、生涯で『宝島』を読んでいないというのは、なんだろう、すごく大きな損失のような気がする。
『宝島』を読むのは、物語に没頭するという、生きている喜びのうちもっとも楽しいことの一つの、圧倒的な体験なのだ。それなしに、生きることを、わたしはオススメしない。
〈参照文献〉スティーヴンソン『宝島』佐々木直次郎・稲沢秀夫訳、新潮文庫、1951年。
目次
まえがき
1 プーの森で、ことばと遊ぶ――A・A・ミルン『クマのプーさん』『プー横丁にたった家』
2 銀河ステーションから、めくるめく幻想世界へ――宮沢賢治『銀河鉄道の夜』
3 二人がそれぞれ、親友のためにやったこと――エーリヒ・ケストナー『点子ちゃんとアントン』
4 物語に没頭する、圧倒的な幸福感――ロバート・ルイス・スティーヴンソン『宝島』
5 教訓を見いだそうとする者は追放されるだろう――マーク・トウェイン『ハックルベリ・フィンの冒険』『トム・ソーヤーの冒険』
6 植物とコミュニケートする農系女子――フランシス・ホジソン・バーネット『秘密の花園』
7 ワンダーランドは卒業を許さない――ルイス・キャロル『鏡の国のアリス』
8 「衣装だんす」で、ファンタジーと出会う――C・S・ルイス『ライオンと魔女』
9 コロボックルはわたしたちの先生なのだ――佐藤さとる『だれも知らない小さな国』
10 愛があれば。愛さえあれば。どんなに世界が苛酷でも。――カルロ・コッローディ『ピノッキオの冒険』
11 才能ある女の子の行く末は――ジーン・ウェブスター『あしながおじさん』『続あしながおじさん』
12 ウェンディの哀しみ――J・M・バリー『ピーター・パンとウェンディ』
13 「不要不急」と灰色の男たち――ミヒャエル・エンデ『モモ』
14 人間が想像できることは、必ず人間が実現できる――J・ベルヌ『二年間の休暇』
15 反省、赦し、和解こそが、知恵である――ルーネル・ヨンソン『小さなバイキングビッケ』
16 落語の世界に通じる『ラッグルス家』の物語――イーヴ・ガーネット『ふくろ小路一番地』
17 「時」とはなにか? 時間旅行SFの金字塔――フィリパ・ピアス『トムは真夜中の庭で』
18 二十一世紀の読者のために作り直された、ル= グウィンからの贈り物――アーシュラ・K・ル= グウィン『ゲド戦記』