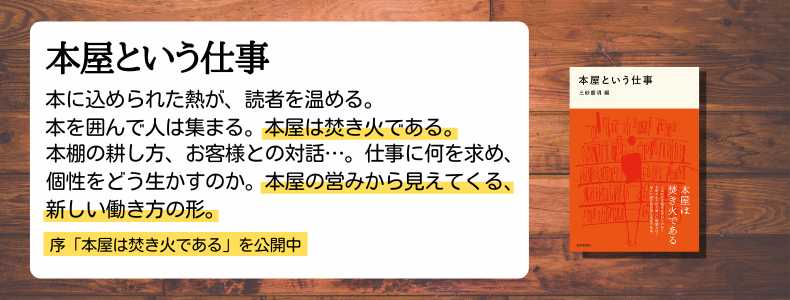本屋は焚き火である 三砂慶明編『本屋という仕事』(序)より
本屋は焚き火であるーー本と人が集い、直接触れあえる場所。書店員は仕事を通してどんな価値を生みだしてきたのか。
本書は、私がコロナ禍での本屋の仕事を見つめ直す中で感じた疑問を、尊敬する書店員の方に教えていただいた本です。
私にとって本屋とは、本を書く人(著者)、本をつくった人(出版社)、本を届ける人(書店員)、本を読む人(読者)が一堂に集まることのできる広場です。箕輪成男の『パピルスが伝えた文明』によれば、紀元前五 世紀のギリシアにすでに本屋はありました。
アテネの市民は、朝食後ただちに本屋にかけつけ、新刊情報を手に入れ、仲間同士でその長所短所を議論していたそうです。また、プラトンの「ソークラテースの弁明」には、「これはおりがあれば、市場へ行って、せいぜい高くても、一ドラクマも出せば、買えるものなので」とあり、すでにギリシアの市場で本が売買されていたことを教えてくれます。古代と現代とで本の形は違っても、本屋は二五〇〇年前からすでに存在していたのだと驚きました。
今なぜ本屋の仕事を考えるのか
本屋が本屋について書いた本は、無数に存在しています。
本屋の定義を更新した北田博充さんの『これからの本屋』。本屋の仕事をこれ以上なく明晰に言語化した宇田智子さんの『本屋になりたい』。選書という本屋の技術の背景を可視化してくれた徳永圭子さんの『暗がりで本を読む』。まるで本屋が生き物であるかのように、息づかいや体温まで感じさせてくれる田尻久子さんの『猫はしっぽでしゃべる』。「本屋の個性は、まちの個性であってほしい」と願い、「まちの本屋」の本質は、地域に根を張る覚悟なのだと教えてくれた田口幹人さんの『まちの本屋』。本屋の本には、くり返し読まれるべき名著が多く、そうした本がある中で、一書店員の私が、なぜ本書を世に問う必要があったのか。それは新型コロナウィルス感染症のパンデミックが、私たちの日常を塗り替えたからです。
毎日当たり前のように店頭に立ち、お客様をお迎えし、本を販売する。今までやってきたことが突然できなくなりました。シャッターを下ろしてお店を閉めたとしても、日々、新刊書籍や雑誌は入荷しつづけました。誰も来店できない店頭で誰にも開かれることのない本を入れ替え、出版社に返品するのは、一体誰のための仕事なのか。混乱がくり返され、さらに政府の定義する「生活必需品」に本は入らないと報道される中、私たち本屋の仕事とはなんだろうか、読者が必要とする本とは一体なんなのかと、問わずにはいられなくなりました。その一方、コロナ禍が私たちの生活習慣を変えたことで、全国各地で新しい価値を問い直す気運が高まっています。
時代の大きな転換期には、今、自分がどこに立っているのかがみえにくくなります。世の中が変わるときこそ、失われていくものに耳をすまし、新しく生まれてきたものを祝福したいと思いました。今、一体、書店の現場では何が生まれようとしているのか。今までとこれからの間に何か変化するものがあるならそれはなんなのか。それが知りたくて、本書を企画しました。
本屋をたずねる
しかしながら、書店の現場で働く一書店員の私に、一体何が問えるのか。考えてみたものの、答えは見つかりませんでした。そんな中、本書を編む方向性を決定づけてくれたのは、ジュンク堂書店の名物店長、福嶋聡さんの『書店と民主主義』でした。この本の中で福嶋さんは、私が立ち上げからかかわっている梅田 蔦屋書店についてこう書いています。
その意味では、梅田 蔦屋書店の品揃えは、ぼくには物足りない。売上シェアは決して高くはなく、ニッチといってもよいかもしれない人文書の棚には、質量ともに主張がないからだ。
ここで指摘されている人文書の棚の担当者こそが、ほかでもない私でした。福嶋さんにこう書いていただけたおかげで、自分の覚悟が決まりました。
私は三〇代で方向転換して、書店で働くことを選びました。人生の大半を本に囲まれて生きてきたのに、このまま本とかかわらずに生きていていいのだろうか。何かやり残したことがあるような気がして、いてもたってもいられなくなった丁度そのとき、本当に偶然、「未経験可」という梅田 蔦屋書店の立ち上げスタッフの募集広告が新聞に出て、思い切って応募しました。
書店で働くことが決まってから、改めて本屋が書いた本を手当たり次第に読んでいきました。まるで小説のようなシルヴィア・ビーチの『シェイクスピア・アンド・カンパニイ書店』。町の本屋の聖書、早川義夫の『ぼくは本屋のおやじさん』。書店の仕事とは仕入れと配置だと語り売上スリップから独自の視点で時代を考察した上村卓夫の『書店ほどたのしい商売はない』。激動の時代を生き、人生には、人、自然、本の三つの出会いがあると説いた松原治の『三つの出会い』。時代をさかのぼりながら本を読んでいくと、目の前にある本棚の見方が少しずつ変わっていきました。
中でも福嶋聡さんの『希望の書店論』は一節を暗唱できるほどくり返し読みこんでいたので、福嶋さんの厳しい指摘には深く考えさせられました。ただし、ジュンク堂書店と比較すると人文書の売場面積が二〇分の一程度しかない「量」の部分はともかくとして、「質」と「主張」については具体的な内容をたずねてみたいと思いました。知識も経験も不十分でしたが、私なりに一冊ずつ選んだ理由があったからです。
勇気をふりしぼってジュンク堂書店をたずねてみると、予想に反して、福嶋さんは「よく来てくれた」と歓迎してくれました。本棚についての議論は尽きず、以来、ことあるごとにお声がけいただき、福嶋さんの著書の一読者としても思いがけない交流がはじまりました。草創期のジュンク堂書店の人文書、法経書の本棚をつくり、支えた岡村正純さんを紹介してくれたのも福嶋さんでした。
岡村さんは、はじめて会った私に人文書とはいかなるものか、その歴史や背景を本棚から教えてくれました。その一端は、『人文書担当者のための日本史概説(中世史中心)』から知ることもできますが、人文書を読むことと人文書の棚を作ることの違いを理解するきっかけになりました。
福嶋さんや岡村さんとの出会いを機に、全国各地にある本屋をたずねてみました。旅行の際に少し足を伸ばして本屋をまわり、棚の配置や並べ方を覚えてから、近所の喫茶店でノートにメモをとっていきました。質問すると、快く本棚についての考えや思いをお話ししてくださいました。学生時代からずっと通い続けていた紀伊國屋書店新宿本店の東二町順也さんに、本の売り方だけでなく、本屋の楽しみ方や愛読書について伺うことができたのは、同業者としてはもちろん、一読者としても望外の喜びでした。コクテイル書房の狩野俊さんには、本は読むだけではなく食べることからはじめることもできるのだと、読書という概念を拡張していただきました。汽水空港のモリテツヤさんには、「本屋は信仰である」という大胆な思想を開陳してもらいました。
それまでずっと、本はただ買えればいいと思っていました。本屋で働くようになり、同僚や先輩から話を伺って、遅まきながら本の後ろには人がいて、その人たちが私の読書と人生を支えつづけてくれたことに気づくことができました。本屋には、毎日、新刊書が送りこまれてきますが、それぞれの場所で愛されている本や、現場に立っている人が育てていきたいと考えている本がありました。本棚をつぶさに眺めていくと、そこには立地や客層といったマーケティングの基準とは別の、本屋自身の世界観が確固として存在していました。その世界観は、一冊の本の隣に何を並べるか、なぜその本を仕入れずこの本を配置しているのか、といったとても小さな声で形作られていました。本と本との関係を組み換え、その場でしか成り立たない新たな価値を生み出し、それを本棚という限られた空間の中で可視化する高度な編集技術に息をのみました。
毎月、必ず新しい本屋を見に行こうと決めてから、いろいろな本屋をたずねてみましたが、際立って美しかったのが、名古屋にあるちくさ正文館書店の人文書の本棚でした。まるで一枚の絵画のようで、本を買うことも忘れて、ただ見惚れてしまいました。新書の棚と詩集の棚から何冊か選んでレジにもっていくと、『名古屋とちくさ正文館』の著者、古田一晴さん本人がレジを打ってくれました。私が長々、本棚を見ていたからか、レジで「あなたは書店の人ですか」とたずねてくださったので、はい、と返事をしました。「もう閉店するからしばらく待ってなさい」とシャッターを閉めてから終電まで、若かりし日の網野善彦さんのお話や、お店まるごとをフェア会場にした空前絶後の一万冊の歴史書フェアについてのお話を聞かせていただきました。
本屋の仕事
本は、乱立するメディアの中では後退しているように見えますが、新聞やテレビ、SNSと比べて、突出した価値をもっています。その一つが「伝えること」です。そのことに気づかせてくれたのが、鳥取県にある定有堂書店でした。
定有堂書店は「書店員の聖地」としてメディアに取り上げられることも多く、私が最初にその存在を教えられたのは『BRUTUS』(七〇九号、マガジンハウス、二〇一一年)の特集「本屋好き。」でした。ブックディレクター(当時)の内沼晋太郎さんが、なぜ定有堂書店が「聖地」になっているのか、その謎に挑んだ豪華企画です。本屋の本質とは何かを問う内沼さんに、店主の奈良さんがまっすぐ答えていくスリリングな哲学対話に興奮しました。
内沼 奈良さんは「書店」と「本屋」を分けて考え、〈定有堂書店〉はあくまで「普通の本屋」であるとおっしゃっていますね。
奈良 「書店」というのは、本という商品を扱い陳列してある「空間」。広いほどいいし立地も単純明快な方がよく、サービスの質をどんどん向上させていくものです。「本屋」はどちらかというと「人」で、本を媒介にした「人」とのコミュニケーションを求める。(中略)
僕はもともと人と話すのが苦手なんです。でも、本を間に置くと、話ができる。だから、お客さんと話します。本好きというのは「自分」という存在への関心が高い人ですから、出会った本について人と語り合いたくなる。「本屋」はその媒介者なんです。僕はその「本屋」という生き方が楽しいんですよ。
今も胸に残りつづけているのは、奈良さんの「本はどこでも買えるから、置き方や出会い方に物語があるのがいい。「本屋」はそれを作る仕事ですね」という一節です。本棚を編集して、本屋という世界観を構築する。その世界観を実際に体験してみたくて、定有堂書店をたずねてみると、本を並べるだけでなく、本棚のそこかしこに奈良さんのメッセージがはりめぐらされていて驚きました。本のジャンルごとの陳列ではなく、テーマで本棚が編集されていました。人文書の読者にビジネス書が視界に入るように、ビジネス書の読者に人文書が届くようにと、まるで汽水域のようにジャンルがまざりあっていて、目的の本を探しにいくことの多い大型書店では隣りあうことのない本が響きあっていました。
奈良さんに、定有堂書店でもっとも売れている本はなんですかとたずねると、一冊の本を差しだしてくれました。定有堂書店が刊行した濱崎洋三著作集『伝えたいこと』でした。売場の黄色いPOPには「定有堂で一番読んで欲しい本」と書かれていました。なぜこの本が売れているのかたずねてみると、定有堂書店が長年つづけてきた「読む会」について教えていただきました。
私は、定有堂書店に行くまで、本屋の仕事とは本を売ることだと考えていました。その考えに今も変わりはありませんが、しかし、本を売ることだけが本屋の仕事ではなく、本を読んでくれる人を途切れさせない工夫を知り、深く考えさせられました。
「競争」ではなく「協奏」する
全国各地の書店の現場に立ちつづけている先輩たちに会って、話を聞いてみて、気づかされたことがありました。それは、私たちはライバルであり、普段、顔をあわすことも、言葉をかわすこともなく、まったく別々の場所で働いていますが、目的は同じではないかということでした。それは本を読者に伝えることです。福嶋さんの代表作『希望の書店論』には、こう書いてあります。
神田神保町で、東京駅前で、池袋で、新宿で、ライヴァル書店たちが「競争」しながら「協奏」する、そしてそうした書店が集積することで、より巨大な「書店空間」を形成して読者の期待に応える、そんなスケールの大きな「野望」を、ぼくたちは抱かねばならないのではないだろうか。
この言葉に感化されて、書店や本のジャンルといった垣根をこえて、「協奏」するフェアを、梅田 蔦屋書店の店頭で開店から約五年間実施しました。面識のない他書店の私の希望にこたえてくれた各書店の先輩たちが選書に協力してくださり、その選書を楽しみにしたお客様が、毎月本棚を見に通ってくれるようになりました。コロナ禍以降は開催することができなくなりましたが、きっとほかにも何か方法はあるはずだと考えていたときに、本書の企画が具体化しました。
本屋は焚き火である
この企画をすすめるにあたり、最初、脳裏に浮かんだのが、定有堂書店の奈良さんの言葉でした。私が定有堂書店でお話を伺っていて印象的だったのは、「本屋は焚き火である」というお話でした。
一冊一冊の本には、それぞれ著者の熱がこめられていて、それがまるで焚き火のように読者を温めている。焚き火は暖かいからまわりに人が集まってきますが、みんなが火にあたりに来るだけではいつか消えてしまいます。でも、来る人がそれぞれ薪を一本ずつ置いていけば、火は燃えつづけることができるのだと奈良さんに教えていただきました。私たち本屋は本を並べることで、読者は本を買うことでお互いを支えつづけています。私は奈良さんの言葉を聞いて、はじめて自分の仕事を通して何か世の中の役に立っているのかもしれないと実感することができました。
私たちの生きている世界は、私たちが積み重ねてきた仕事の上に成り立っています。私たちが住む家も、着る服も、食事も、誰かの仕事の結果です。私たちは生きている時間の大半をそれぞれの仕事に費やしています。だから、良い仕事をすることは、より善く生きることと密接につながっています。私は本屋で働いているので本が中心ですが、本屋の仕事について改めてもっと深く知りたくなりました。尊敬する書店員の方たちは、なぜ本屋を選んだのか。働くことを通してどんな価値を生みだしてきたのか。本への愛憎。本棚の耕し方。お客様との対話。お店を成り立たせるためのマネジメントについて、書店員の先輩方にたずねてみることはきっと、ほかの職業にも通底する本質的な問いだと信じています。
本書は、本屋をはじめるには火を熾さなければならず、本屋をつづけていくには火を焚きつづけなければならないとの奈良さんの言葉に導かれて、三部構成にしました。
第Ⅰ部は、何もなかった場所に、本屋という火を熾してきた人の言葉です。
第Ⅱ部は、書店員として働く中で、いかに薪をくべつづけているのか、その果てしない取り組みについての経験知を記していただきました。
第Ⅲ部は、誰も歩いたことのない道をただ一人、歩きつづけている人の実践の記録です。業界用語については、書店ごとに名称や使われ方が違うものもありますが、田口幹人さんが明快に解説してくれています。
また、収載させてもらった二つの鼎談「完璧な本」と「あなたのための本」は、本書の企画の核でもあり、この鼎談がなければ本書が完成することはありませんでした。鼎談を企画してくれた北村知之さんと北田博充さん、また本書への収載を快諾してくれた辻山良雄さん、堀部篤史さん、黒田義隆さん、磯上竜也さん、長江貴士さん、鎌田裕樹さんに深く感謝します。
この本で目指したいと考えたのは、本屋を入り口にして私たちが生きる世界に、新しい価値をつけくわえるための道標を提示することです。どうぞ最後までお付き合いください。

目次
序 本屋は焚き火である/三砂慶明
第Ⅰ部 火を熾す――本屋のない場所に本への扉をつくる
1章 汽水空港という信仰/モリテツヤ(汽水空港)
2章 言葉をひらく場所/宇田智子(市場の古本屋ウララ)
3章 背表紙を眺める/田尻久子(橙書店・オレンジ)
4章 本屋から遠く離れて――定有堂教室「読む会」のこと/奈良敏行(定有堂書店)
鼎談1 完璧な本
辻山良雄(Title)×堀部篤史(誠光社)×黒田義隆(ON READING)
司会・構成・追記:北村知之(梅田 蔦屋書店)
第Ⅱ部 薪をくべる――日々の仕事から新しい価値がうまれる
5章 書店の棚論――「棚づくり」について/岡村正純(大阪高裁内ブックセンター)
6章 本屋の生態系――本屋に集まる人が作り上げるもの/徳永圭子(丸善博多店)
7章 書店員の本屋の楽しみ方――「観察」のすすめ/東二町順也(紀伊國屋書店新宿本店)
8章 本にかかわる全ての仕事/北田博充(書肆汽水域・梅田 蔦屋書店)
鼎談2 あなたのための本
磯上竜也(toi books)×長江貴士(元さわや書店フェザン店)×鎌田裕樹(元恵文社一乗寺店)
司会・構成・追記:北田博充
第Ⅲ部 火を焚き続けるために――本屋の仕事を拡張する
9章 読者への窓を広げて――食べるように読み、つくるように書く/狩野俊(コクテイル書房)
10章 これからの読者のために――出版物流から読書環境のサポートまで/田口幹人(合同会社未来読書研究所・北上書房)
あとがき
BOOK LIST
BOOK STORES MAP
装幀・本文デザイン:タキ加奈子(soda design)