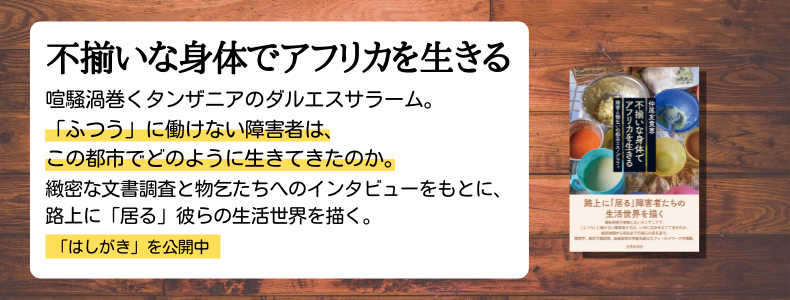『不揃いな身体でアフリカを生きる』はしがき
自分自身を「ただ一つのストーリー」でもって表現されたい人というのは、存在するのだろうか。語りという形での自分自身、あるいは他者の表徴は、時に戦略的に機能する。自分をこのように見てほしい、このように受け取ってほしい、という特定の志向の下で、あえて戦略的に自らを単純に表現する場合というのはあるだろう。そのような方向付けを別にすれば、人間とは本来多面的な存在であり、その人となりや人生はいかようにも語り得る可能性をもっている。
ある人についての多様な語られ方の可能性を、切り捨て、特定の「ただ一つのストーリー」に置き換える時、戦略的にであれ無意識的にであれ、表現された人の多面性のうち特定の側面が押し出されている。そのため、多くの要素から成る「あの人は○○でもあるが××でもあり△△でもある」という語りよりも、「あの人は○○である」という断定の方がより鋭く響く。
このような断定はしばしば、様々な「社会的弱者」について語る際に採られる。例えば、二〇〇八年頃から国際的にも大いに社会問題化され、日本でも近年知られるようになった「アルビノ・キリング」というものをめぐる語りはその典型を示している。東アフリカにあるタンザニア連合共和国という国の「有名な」社会問題であり、これについては今日までに膨大な文献、報道、ドキュメンタリー等が蓄積されている。しかしその量に対して描かれてきた内容は意外にも単純で、タンザニアというアフリカの一国では、先天的に身体の色素(メラニン)が通常より少ない人々(「アルビノ」や“people with albinism”)が老若男女問わず凄惨な暴力に遭っている、というものだ。そこではある属性をもつ者が「被害者」や「弱者」、別のある属性をもつ者は「諸悪の根源」として固定され、両者の間には「教育」や「人権」という「近代的」で圧倒的な「正義」によって切り込まなければならないとされる。それは確かにわかりやすく、遠く離れた場所にいる人々にも届き、その正義感をくすぐって行動への衝動を喚起する。その結果、「アルビノ・キリング」の問題化以降に「被害者」であり「弱者」である「アルビノ」を取り巻く状況については世界各地で変化があったのは事実である。
他方、そのわかりやすさは正義の名の下に消費されることもある。農村の貧しい家に住むアルビノである子どもが外国人記者からマイクを突き付けられて泣きじゃくりながら家族の最期の様子を言わされる映像を見たことがあるが、この映像は映画化されてタンザニア国内だけでなく様々な地域からアクセス可能になった。全世界では何千、あるいは何万という人々の目に触れたはずだ。
「アルビノ・キリング」の典型的な語りは「正しい語られ方」として固定された。一〇年以上経った現在でも、その語りのパターンに大きな変化はない。一度生み出された単純明快なストーリーは型押しされたように再生産を繰り返し、その圧倒的な量と強さでもって他の形の語りを排除していく。他の形の語りはないわけではないが、圧倒的に後景化され、時には「不謹慎」とされて集中的に取り除かれてしまうことさえある。
ある者が被抑圧的側面や弱者性をもつ時、その困難の遠因は大抵、社会構造にある(と少なくとも社会学者や社会人類学者ならば考えるはずだ)。したがって、少なくとも社会の描写を行う者として当該社会構造の問題性を指摘せず、当該の人々が抱える困難や問題を私的で個人的なものへと矮小化することは、書き手の怠慢、あるいは権力の濫用である。この批判は繰り返されてきた。では、被抑圧的側面や弱者性をもつ者を「弱者」や「被害者」という「ただ一つのストーリー」に収斂させることについてはどうか。これは右の批判を逃れているようにみえることから、しばしば「正しい語られ方」とされてきた。
しかし、後者もまた、直球の他者化であり、描かれる人々を突き放すものとして機能し得る(少なくとも表現される者の志向に沿っていないならば)。ある人の人生を矛盾を孕んだ複雑な形で捉えて表象することは時に「不謹慎」であり「わかりにくい」ものかもしれないが、それこそが相手に近づくことではないのだろうか。少なくとも、突き放さないことにはより近いのではないだろうか。
本書はタンザニアの最大都市、ダルエスサラームという場所で生活しているいわゆる「(身体)障害者」の人たちの生活について書き、考えようとする。第三者から「障害者」と言及され得るような身体的特徴をもつ人々は、現地では「ワレマーヴ(walemavu, 単数はムレマーヴmlemavu)」と呼ばれることが多い。本書では試みに「障害者」ではない名称(顕在的「欠損」保有者)も併用するが、いずれにせよ彼らは、これまでの当該地域社会研究で不可視化されたり周縁化されたりしてきた。
本書が学術書として語ることを構造的に可能にする問題設定(これはふつう研究の最終段階で固まる)は序章で述べるが、それに至るまでの研究の動力となった基本的方針、ないし「裏テーマ」は、「ワレマーヴから聞いたライフストーリーを、語った当人以外の人々にも理解できるような形で書く」という課題である。この課題は筆者が意識的あるいは能動的に設定したものというよりは、逃げられず格闘せざるを得なかったものである。
この課題にからめとられた経緯について、個人的な話を通して示しておきたい。まずは二つの白状から始めたい。一つ目は、「ワレマーヴ」(あるいは顕在的「欠損」保有者、「障害者」)とされる人々に対する筆者の立場は、親近感や共感からというよりも、簡単に言えば「他者化」ありき、つまり「違和」や「発見」や「好奇心」から始まっている。
筆者が後のフィールドとなるダルエスサラームに行ったのも、「ワレマーヴ」に関心をもったのも、まったくの成り行きである。当初調査しようとしていた「アルビノ・キリング」というテーマは様々に問題を抱えていた。そのため公的な調査許可取得のために立ち寄ったダルエスサラームで足止めされ、それがきっかけとなってダルエスサラームの混沌と開放性と刺激的な性質に魅了されてしまった。この街の暮らしについて知りたくなり、「ふつう」の働く人々の中に友人を見つけた。
彼らの多くは初等学校のみを卒業してたたき上げで食べている成人で、自立して立派にやっているようだったが彼らの生活レベルにおける苦労も知るようになった。一日一四時間、週六日立ち働いても薄給にしかならず、生活費と家賃を賄うことさえままならずに知人友人に掛け合ってなんとかやり繰りするような生活状況はありふれており、安定的に学費を払うだとか貯蓄をして将来に備えるといったことは夢物語に近い。
このような「ふつう」の生活状況を知るほどに、それとは「異なる」様子の人々の存在が気になるようになった。友人たちが働く市場の隅に、スーパーの出入口に、交差点に、中央分離帯に、街中心部の路上のそこここに「居る」人たち。やってくる人々に手を突き出し声をかける者もあれば、ただ佇んでこちらに目をやる者、笑顔で挨拶をしてくる者。手足が欠けていたり、年老いていたり、ぐったりした様子の子どもを抱えていたり。彼らに言及する語にはバリエーションがあったが、「ワレマーヴ」という語が使われることが多かった。「ワレマーヴ」の英訳は“disabled people”(「障害者」)であることは知っていたが、釈然としなかった。労働については言うまでもなく、移動や水へのアクセスでさえこれほど身体の酷使が必要なこの街で、働けど働けど生活費に苦労するこの街で、人より筋力がなかったり、動けなかったりする人はどうやって生活しているのか。彼らは明らかに「働けない」、あるいは「働かない」が、一体どうやって生活しているのか。このように私は「ワレマーヴ」に関心を寄せるようになった。
二つ目の白状をしたい。筆者が当初「ワレマーヴ」についての調査先として訪ねたのが、専ら福祉、教育、医療に関わる施設や組織に偏っていたことだ。つまり、私はそこに「居る」人たちの前を素通りして、「専門」機関や「支援」団体を訪ねた(もちろん「障害者」のセルフ・ヘルプ・グループも積極的に訪ねた)。この調査は比較的うまくいき、インタビューもたまった。
しかし当初の問題意識に沿って進んでいる感触はなかった。組織や施設でのインタビューからは現状のタンザニア社会が抱える「障害者」をめぐる諸問題は明らかになるが、そこここで目にする人々が一体それらとどのように折り合いをつけて生きているのかが一向にみえてこない。「障害者」の組織や施設(彼ら「のための」であれ彼ら「による」であれ)へのインタビューをしても、いや、すればするほどに、私が知りたいこと、つまり「この環境の中でワレマーヴとして暮らすというのがどういうことか」という問いからは遠のいていくように感じた。スロープもない乗り合いバスに肢体や目が不自由な人がその場で人の手を借りて何事もないように乗車してくるあの感じ、去年見かけた物乞が今年も同じように毎日同じ場所にいるあの感じ、それらにはどうやって接近できるのか。全三回の渡航期間の二度目が終わる寸前まで、「ワレマーヴ」に関心をもってからのべ一年以上もの間、私は悩み続けた。
調査の行き詰まりが解消され始めた転機は、地元民であり三度目の渡航時のホストマザー兼調査助手となる女性、サミアさんとの出会いである。彼女にとって、手足が欠けた体で路上に佇む人は「話しかけることを躊躇する相手」ではなかった。そして彼女の振舞いに倣って一歩を踏み出すと、驚くほど多くの人が快く自らのストーリーを語り始め、あっけなく聞き取りが実現していった。
この段階に至って初めて、私がそれまで実に自己完結的で「閉じていた」ことに気がつかされた。一年以上も膠着していた理由は単純だった。私が一歩を踏み出せていなかった。それ以前の私は特定の属性をもつ人々である彼らに近づき難さを感じていたが、それは彼らに起因することではなく、私が彼らに接近しようとしていなかっただけなのだ。それに気がついた時、なぜそれまでの調査では「専門」の「支援」組織や施設だけを見ていたのか、自分がそれなりに根拠をもって取り組んでいたはずの行動のすべてが不可解に感じられてならなくなった。施設や組織を訪ねればその施設や組織についての情報を得られるが、それは「生活」とは異なるもので、少なくとも部分的にしか重ならないのは当然だ(全制的施設でない限り)。
この単純な気づきは、しかしながら、重要な転機だった。それ以前の私は「ワレマーヴ」を自分とは切り離された単純化された存在として捉えてしまっていたが、この気づきの後に現れたのは、複雑さと多様性であった。こうして出会った興味深い「ワレマーヴ」(という語で指すこともできる多様な人々)を前に、私は長い間、固有名詞以外の名称(つまり総称)さえ呼びあぐねることとなった。私の手元には既存のそれらしい名称はいくらかあったが、「彼ら」について知ろうとする時、語ろうとする時、それらはあまりに頼りなく思えたり、時に邪魔くさくさえ感じられるようになった。そうして、自分が何に取り組んでいるのかわからないまま、特定の人々を表す言葉を既成のものから当てはめてみたり、自分で創ってみたり、一度貼り付けた名称のラベルを剥がしたりしながら、違和感を小さくしつつも他の人々にも通じる方法を模索する道が始まり、それは今に至るまで続いている。
とはいえ、この模索の道は結局は知りたいことに通じる道であったようだ。後から考えれば、「ワレマーヴ」とされる彼らとの出会いがフィールドという混沌と不安定な関係性の中で始まったことは幸運だったかもしれない。
結論を先取りすると、調査開始にあたって設定した「ワレマーヴ」であること(すなわち「特定の身体形状をもつ」という属性をもつこと)という調査対象の選定基準は、分析が進むにつれその意味がぼやけていった。そして「ワレマーヴ」である人々は、これまでのアフリカ地域研究で描かれてきた都市民や、あるいはより広い意味での都市民(都市的環境が席巻する日本に住む私たちも含まれる)と重なっていった。「ワレマーヴ」、あるいは「障害者」とされる人々の働き方、生活の仕方、主体性のあり方について学術的分析をしていくと、それらの一つひとつについて「ワレマーヴ」や「障害者」ではない人たちとの差異が明瞭さを失っていき、調べれば調べるほど、「ワレマーヴ」や「障害者」とされる人々がそれ自体で閉じてはおらず、むしろ様々な要素の結節点であるということが確認される。
これは実は当然の話である。どんな属性をもつにせよ、社会的存在である人間とは様々な要素の結節点であるのだから、複雑に書けば書くほど共通点がみえてくるのは必然である。
それではなぜ、この当然のことにすぐ気づけなかったのだろうか。研究を進めていくと、これはどうやら筆者個人の感性の鈍さだけに帰すのは適切でない問題であるように思われてきた。「ワレマーヴから聞いたライフストーリーを、語った当人以外の人々にも理解できるような形で書く」という課題には何らかの難しさがある。それでは、その難しさとはどのようなものか。「ワレマーヴの語りを聴く」ことと、「それをストーリーとして当人以外に伝える」こと、どうやら難しさはこのあたりに隠れていそうである。
例えば、筆者のような余所者(外国人であり相対的には富裕層)から話しかけられて快く自らのストーリーと生活を見せてくれる「ワレマーヴ」がいる。彼らのこのような態度を、今これを読んでいるあなたはどう捉えるだろう。筆者が本書を書くまでに周囲の人々から得た反応を挙げてみたい。タンザニアも日本も問わず、多くの人(多くは非「ワレマーヴ」または非「障害者」)は「ワレマーヴ」や「障害者」について知りたければまず福祉、教育、医療の施設を訪ねるようにと助言をくれた(実際、(少なくともアフリカの)「障害者」についての聞き取りを基にした文献のうち圧倒的に多くは施設や組織に所属する人だけからの聞き取りに基づいている。組織や施設を訪ねるのは王道である)。そして「ワレマーヴ」から直接話を聴くことについて、少なからぬ人は「なぜ話だけを聴くのか(なぜもっと直接的で物質的な支援をしないのか)」と問い、「支援すべき(しないなら話を聴くべきではない)」という助言までする人もあった。また、筆者が聞き取った話を基に研究発表をすると大抵、「困難な潜入捜査」を成し遂げたかのようにみる人がいた。右に挙げた反応の向こう側には、ある属性をもつ者を、語れず、常に助けを必要としている人と固定的に捉える眼差しが透けてみえる。
問うべきは本当に「彼ら(ワレマーヴ)」なのだろうか。サミアさんと出会って得た単純かつ重要な気づきは、その後の筆者からみえる景色を次々と逆転させ始めた。なぜ以前の私は彼らを近づき難く感じたのか。余所者から話しかけられて快く自らのストーリーと生活を見せてくれる「彼ら(ワレマーヴ)」が特殊なのではない。「彼ら」が余所者にもオープンでいてくれるのは、「彼ら」にとって自らのストーリーと生活状況をシェアすることは決して恥ずべき行為ではないから。「彼ら」が堂々と生きているから。こう前提するだけで自然に説明できることではないか。問うべき方向は逆であり、余所者にストーリーを語る「彼ら」の姿を意外に思ってしまう、「彼ら」を「(他の人と違って)閉じている」と想定してしまう「私(たち)」と、その思考である。
裏テーマに潜む難しさは、その単純明快さで他を圧倒する「ただ一つのストーリー」が「彼ら」、すなわち「ワレマーヴ」(あるいは顕在的「欠損」保有者、「障害者」)について既に確立していることから生じているのではないかと現時点では仮定している。「正しい語り」に意義がないわけではないが、その引力が他の形の語りを圧倒するほど強力であることには注意深くある必要がある。他者の人生について、語られ方の潜在的可能性を奪う権利は誰にもない。
このように裏テーマと格闘するにあたって、本書における記述の全体方針を二つの志向から採ることにした。一つはフィールドで出会った、私に描かれることになる人々とのやりとりの中で、彼らが私に示した(と私が感じた)「こう見られたい」「こう受け取ってほしい」という志向である。もう一つは、そのような(私に受け取られた形での)彼らの志向を、彼らを知らない人たちにも理解可能な形で提示するための、アカデミックな技法を身に付けた通訳者あるいは注釈者としての志向である(こちらは証拠を挙げて説得することを好む)。
本書の書き方の方向性は、フィールドで彼らが示したその堂々とした様子を骨子とすることにする。このような方針は、書き手が書かれる対象との権力関係の非対称性を自覚することが期待される昨今のエスノグラフィとしては、あまりにナイーヴととられるかもしれない。実際に彼らと筆者の間には、書かれる者と書く者という非対称性、「今・ここ」の生活を覗き見られる側とプライベートから切り離された「フィールドに居る者」との非対称性等々、様々な非対称な関係がある。しかし、彼らを「弱者」や「被搾取者」として描くのは、それこそ対面時に取り結んだ関係性から逸脱していて後ろめたい。筆者は彼らに対して「弱者」というストーリーに入れたいとは交渉していないし、少なくとも対面時には、彼らは筆者に対して弱者性だけを押し出した「ただ一つのストーリー」でもって自らを表現したわけではなかった。自らについて語ってくれた彼ら、彼女らに対して誠実な書き手であろうとする時、現時点の判断として、語ってくれた当事者たちを手頃なカテゴリーに押し込めたうえで把握するのではなく、それぞれの個のばらつきと顔が見えるように、さらにできる限りそれぞれが輝いて見えるように描くべきと考えるに至った。
しかしながら、「ただ一つのストーリー」とこのような方法で格闘したはずの本書そのものが、あり得る多様な可能性の中での他を切り捨てた、一つのストーリーであることには違いない。その意味では本書も結局、描かれた人々を固定してしまうのである。ただし、固定化にあたり筆者の意図としては、描かれた人々の姿が読者にとって「ありふれたもの」のように身近さを伴って受け止められる可能性に挑戦したつもりである。本書のトピックは読者の多くにとっては「新奇」的にみえるかもしれないが、本書の主眼は珍しい知識の伝達にはなく、特定の人々を周縁化してきた私たちの目を問い直し、改めてこれまで見てきたものを見直す、あるいはこれから世界の見方を少し変えるという行動への誘いにある。だからこそ、本書で扱うトピックは、読者が慣れ親しんできた風景(あるいは研究分野)と接続され、開かれていく必要がある。遠くの世界の聞いたこともない話ではなく、むしろ、読者の方の身の周りにもあることと重ねながら読んでもらえたら。その目論見が成功しているかどうかは、読者の評価を仰ぎたい。
ダルエスサラームでは「誰しもそれぞれの人生がある(kila mtu ana maisha)」という言葉がよく聞こえてくる。人々が余所者や「ワレマーヴ」など、「違う人」をあっけらかんと受け容れてくれる雰囲気をよく表している言葉だ。ダルエスサラームにはいわゆる社会保障もバリアフリーもない。「ワレマーヴ」はそこで当然のように生活している。「ワレマーヴ」は確かに他の人々とは違う側面も持ち合わせているが、人が誰しも同じではないように、当たり前のように個性をもっている。ダルエスサラームのひしめく差異の中でみられる寛容性から、「他の人と同じであること」が当然のように期待されてしまう現代日本社会に住む私たちが学べることは大いにあると考えている。