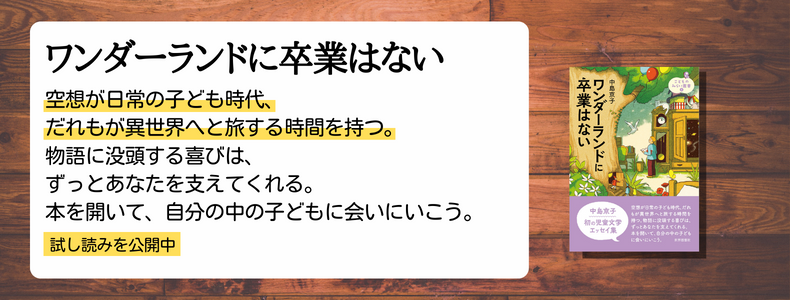「不要不急」と灰色の男たち――ミヒャエル・エンデ『モモ』
空想が日常の子ども時代、だれもが異世界へと旅する時間を持つ。
物語に没頭する喜びは、ずっとあなたを支えてくれる。本を開いて、自分の中の子どもに会いにいこう。
『クマのプーさん』から『ゲド戦記』まで――作家を育てた18の物語。
直木賞作家・中島京子による初の児童文学エッセイ、『ワンダーランドに卒業はない』より、「「不要不急」と灰色の男たち――ミヒャエル・エンデ『モモ』」を紹介します。
願わくは、本というものには、長生きしてもらいたいものだ。だから、必要もないのに時事的なことを書くべきではないと思うのだけれども、『モモ』という普遍的かつ警鐘的な物語を前にして、コロナ禍のドタバタに「灰色の男たち」がかかわっていそうな気がするのを、止めることができないでいる。
世界はこの新型ウイルスによって変化を余儀なくされた。でも、ウイルス自体が「灰色の男」的だと言いたいわけではない。ウイルスに感染しないためにと奨励された対策のあれこれが、なんだか「灰色」っぽかったのだ。
「不要不急」という奇妙な四文字熟語が、わたしたちの生活を侵害した。これは、もちろん、仕方のないことだったと言えるだろう。とくに、ワクチンの開発も間に合わなかったころは、とにかく人同士が出会わなければ感染の危険は確実に減るし、感染の危険を減らすことで重症化する病人の数も減らさないと、医療が崩壊してたいへんなことになる。移動、行動の制限は、ウイルス対策の最前線に立った医療従事者からの叫びでもあったから、それはやらなければならないことだった。
ただ、この、「不要不急」という四文字熟語は、なにが「要」で、なにが「急」なのかを、いやでも考えさせるものだったから、そしてしばしば、ひどくたいせつなものが「要」でもなければ「急」でもないとされたから、わたしたちはひどくモヤモヤとした、灰色の男たちの吸う葉巻の煙のようなものを、抱え込むことになってしまった。
『モモ』は、一九七三年に書かれた物語で、一九七六年にはもう邦訳が出ている。わたしが初めて読んだのは、しかし、本が出てから少ししたころで、もう高校生だったのではないかと思う。子どもの本を読むには少し、とうが立ちすぎているような気がしないでもないけれど、このかなりあからさまに現代批評的な作品を読むには、ちょうどいい年齢だったかもしれない。
モモは、人の話を聞いてあげるのが得意なちょっと不思議な女の子で、円形劇場の跡に住み着いている浮浪児だ。モモのもう一つの得意技は、遊ぶこと。遊ぶことというか、遊ばせることだ。モモの近くにいると、誰でも楽しい遊びを思いつく。おもしろい空想物語を作り上げることもできるし、みんなで楽しむ新しいゲームを創造することも簡単だ。モモほど天才的ではなくても、こういう子はいる。その子といっしょにいると楽しい遊びが次々にできてしまうというようなことは、あった。いまでも、そういう子どもが楽しいことを考えつき、友人たちを巻き込んでいるといいなあと思う。
みんなはモモを慕い、なにかあれば「モモのところに行ってごらん!」と声をかけ合って、家のないモモのために、住むところを整えてやり、食事を運んでやっていた。それが変わってしまったのは、「灰色の男たち」が跋扈し始めたせいなのだ。
「灰色の男たち」は、人々から時間を奪う。「時間を節約して、貯蓄しておきなさい」とささやきかけ、無駄な時間を作らずに効率よく仕事をして成功するようにと説く。子どもたちも、最初は大人からちっともかまってもらえなくなり、機械仕掛けのおもちゃを与えられてネグレクトされるけれど、そのうち「子どもの家」に放り込まれて、遊んでばかりはいられなくなり、将来役に立つための勉強ばかりさせられるようになり、「小さな時間貯蓄家」になっていく。
この、非常に具体的な設定の「寓話」が、ミヒャエル・エンデの児童文学を特別なものにしているのだが、子どもとして読むと少しだけ、怖いような、残酷なような、やや大きすぎる主題にたじろぐようなところもある。
しかし、ちょっと引いてしまいがちな童心を、がっしりつかんで歩き出すのは、カメのカシオペイアのゆったりとした歩みだ。
モモが「灰色の男たち」の秘密を知り、それを人々に知らせようというこころみが失敗した夜、カシオペイアはゆうぜんと円形劇場に現れる。
「ツイテオイデ!」
という文字が、カメの甲羅に浮かび上がる。
「灰色の男たち」に、モモの名前と居場所が知られてしまった、おそろしい裁判のシーンのあとに、ひっそりと差し出されるこのエピソードが、なんともいいのだ。あ、モモはだいじょうぶなのかもしれない、と、心が安らぐ。
子どものための本としては、こういうところはだいじなんじゃないかと思っている。
『宝島』の語りが、ジム少年の危機とその回避をいつもあらかじめ明かしてしまうように。子どもは(子どもばかりではないだろうけれど)、あまりにつらいシーンの連続には耐えられない。ちょっと希望がないと、ついていくのが難しい。最後の最後にはハッピーエンドが待っていると思って、我慢して読み進むのにも限界がある。
わたしはいつ読んでも、このカメのカシオペイアが登場するところでホッとする。そして、モモが冒険物語の主人公になる予感にわくわくする。女の子が冒険物語の主人公になるのは、いまだとさほどめずらしくないだろうか。モモが登場したときは、画期的だった。比肩する傑物は長くつ下のピッピくらいか。しかし、女の子が一人で冒険の旅に出て、世界を救う、というようなのはなかったんじゃないか。そういう役割は、ずっと男の子にだけ負わされていたから。
「灰色の男たち」の追跡をよそに、ベッポとジジも置き去りにして、モモの冒険は進んでいく。そしてこの冒険には「シンパイムヨウ!」という文字を甲羅に浮かべるカシオペイアがついているのだ。カシオペイアがいなかったら、この旅はなんと不安なことだろう。ゆっくり進んだり、「ウシロムキニ」進んだりしながら、モモは「どこにもない家」、マイスター・ホラの館にたどり着く。
マイスター・ホラとの問答も、ちょっと形而上学的で難しいところはあるのだけれど、モモが時間の花を見るシーンを含め、おおむね幸福感に満ちている。「どこにもない家」で食べる朝食も、なんともおいしそうだ。
マイスター・ホラがつかさどっている「時間」の正体は、「命」と言い換えてもいいようなものだ。命とか時間とかいったものは、それ自体は「善い」とか「正義」とかいうものでもない。「灰色の男たち」は悪い存在として描かれているから、モモの側が「善」で、男たちが「悪」と、単純に読んで読めないこともないけれど、モモやマイスター・ホラが体現しているのは「善」というより、「幸福」なのだろう。だから、対して「灰色の男たち」は「不幸」、それも、命を楽しまない、あるいは楽しめないことからくる圧倒的な不幸を表していると言えるだろう。
物語は、マイスター・ホラが時間を止めてしまい、モモだけが一時間しかもたない「時間の花」を持たされて、その短い時間で「灰色の男たち」が貯蔵している時間を開放し、奪われた時間を人々のために取り戻してあげるところで終わる。円形劇場にはベッポもジジも、子どもたちも、仲よしの大人たちも戻ってくるが、この再会シーンは意外にあっさりと終わる。終わりよければすべてよし。それとも、「時間どろぼう」の暗躍は、ちょっと気を許すと、いつでも起こりうるということを、作者が知っているせいかもしれない。
『モモ』の物語は、わかりやすいといえばわかりやすい。「心に余裕を持とう」とか、「あくせく働くばかりではほんとうの幸せを見失うよ」とか、「成功ばかりが人生じゃない」とか、そんなことを語っているように見える。そして実際そうだろう。みんな、モモの物語を「そうだなあ」と思いながらも、日々時間に追われ、時間を誰かに奪われているように感じて生活をしている。それが現代人というものだ。子どもたちが想像力で遊ばずに、みんなゲームの端末を持っている光景に、「灰色の男たち」の跳梁跋扈を、感じ取る人もいるだろう。
しかし、この、コロナ禍で読み直して、わたしはまたちょっと新たな気づきを得た気がした。というのは、本の中ではいかにも悪そうに現れる「灰色の男たち」が、むしろ「正しさ」のマスクをかぶって現れることがあると、気づいたのだ。
長々書いてきたけれど、冒頭で触れたことに戻ると、コロナ禍の下では、「不要不急」は「悪」になった。つまり、「要」と「急」のみが優先される事態が「善」になったのだ。最初に書いたように、もちろんそれはウイルスの蔓延を防ぎ、医療の現場をひっ迫させないために重要な方針だったことは、誰の目にもあきらかだ。こう言い換えてもいいかもしれない。状況によっては、「灰色の男たち」のほうが「善」に見えるような事態が起こりうるのだ、ということ。
そう考えて、わたしはちょっとギョッとした。そしてそれは、とてもとても気をつけなければならないことだと、気を引き締めたのだ。
コンサートやライブ、映画鑑賞、演劇などのパフォーマンスは、「不要不急」のグループに入れられた。スポーツイベントも、講演会も。仕事を終えた時間にみんなでリラックスしてお酒を酌み交わす時間も、ダメということになった。子どもたちが遊ぶ公園も、黄色いテープが張られて閉鎖された。美術館も博物館も、動物園なども休業した。
仕方のない処置だ、と思えるものも多い。いくら自由や幸せがだいじでも、人の命には代えられない。でも、中には、疑問符がつくものもあった。たとえば、マスクをして、黙ってスクリーンを見つめるだけの映画鑑賞を換気もいい劇場でやるのは、どうしていけないんだろうとか。おおぜいでお酒を飲んで、大きな声で話したり歌ったりすれば感染リスクが高くなるのはわかるけれど、お酒自体がウイルスを媒介するわけではないのだから、一人で黙って飲むのはいいんじゃないかな、とか。
あれをダメ、これをダメ、とやっているうちに、たいせつな仕事を失う人も多く出てきた。仕事を失い、家を失う人も。
モモの物語は、ホームレスの物語でもある。モモは家のない子なのだ。保護者もない。学校にも行っていない。でも、その子を、みんなが助けて生きさせる話で、そのお返しと言ってはなんだけれど、ホームレスの女の子に、社会が救われる話なのだ。
これを、どう考えたらいいんだろう。「不要不急の外出は避ける」「密を避ける」といったことは、たしかに社会を守るための対策なのだ。「灰色の男たち」みたいに、「人間から時間を奪ってやる!」という悪い意志に基づいたものではないはずなのだ。
しかし、だからこそ、わたしたちは、もう一度『モモ』を読み直して、肝に銘じなければならないと思う。わたしたちの時間は、わたしたちの命は、幸福をこそ追求すべきものだ。それがなにか不可抗力によって「奪われる」事態に直面したとき、わたしたちは奪われ方をできるだけ少なくすべきだし、不可抗力と思われる事態が通り過ぎたら、速やかに「取り戻す」必要がある。そうじゃないと、いつ誰が「わからないのですか。緊急事態なんです。ですから、あなたの時間はあなたのものではなくなります」と言いだすかわからないから。その「緊急事態」は本物か、そしてどうすればそれが回避できるのか、どれくらいの間「時間」を譲り渡さなければならないのか、真剣に考えなければならない。ああ、「灰色の男たち」が、ほんとに灰色のスーツを着て葉巻を吸っているなら、見分けるのはひどく簡単なことだろう! でも、現実は、そうではない。
そして、「時間どろぼう」の暗躍によって、家も仕事もなくした人たちが出るなら、社会全体で支える必要があるだろう。だって、それは、モモなんだから。
『モモ』の有名なあとがきの中に、「わたしはいまの話を、過去に起こったことのように話しましたね。でもそれを将来起こることとしてお話ししてもよかったんですよ。わたしにとっては、どちらでもそう大きな違いはありません」と語る、謎の男が出てくる。この謎の男が誰なのかは、読んだ人にはわかる仕掛けになっていると思うのだけれども、しかしまあ、それはエンデ自身でもあるだろう。
現代社会に鋭い警鐘を鳴らした文学として語り継がれる作品だけれど、これはたしかに、手元に置いて、常に読み返す必要のある本だと、あらためて思ったのである。
〈参照文献〉ミヒャエル・エンデ『モモ』大島かおり訳、岩波書店、1976 年。
目次
まえがき
1 プーの森で、ことばと遊ぶ――A・A・ミルン『クマのプーさん』『プー横丁にたった家』
2 銀河ステーションから、めくるめく幻想世界へ――宮沢賢治『銀河鉄道の夜』
3 二人がそれぞれ、親友のためにやったこと――エーリヒ・ケストナー『点子ちゃんとアントン』
4 物語に没頭する、圧倒的な幸福感――ロバート・ルイス・スティーヴンソン『宝島』
5 教訓を見いだそうとする者は追放されるだろう――マーク・トウェイン『ハックルベリ・フィンの冒険』『トム・ソーヤーの冒険』
6 植物とコミュニケートする農系女子――フランシス・ホジソン・バーネット『秘密の花園』
7 ワンダーランドは卒業を許さない――ルイス・キャロル『鏡の国のアリス』
8 「衣装だんす」で、ファンタジーと出会う――C・S・ルイス『ライオンと魔女』
9 コロボックルはわたしたちの先生なのだ――佐藤さとる『だれも知らない小さな国』
10 愛があれば。愛さえあれば。どんなに世界が苛酷でも。――カルロ・コッローディ『ピノッキオの冒険』
11 才能ある女の子の行く末は――ジーン・ウェブスター『あしながおじさん』『続あしながおじさん』
12 ウェンディの哀しみ――J・M・バリー『ピーター・パンとウェンディ』
13 「不要不急」と灰色の男たち――ミヒャエル・エンデ『モモ』
14 人間が想像できることは、必ず人間が実現できる――J・ベルヌ『二年間の休暇』
15 反省、赦し、和解こそが、知恵である――ルーネル・ヨンソン『小さなバイキングビッケ』
16 落語の世界に通じる『ラッグルス家』の物語――イーヴ・ガーネット『ふくろ小路一番地』
17 「時」とはなにか? 時間旅行SFの金字塔――フィリパ・ピアス『トムは真夜中の庭で』
18 二十一世紀の読者のために作り直された、ル= グウィンからの贈り物――アーシュラ・K・ル= グウィン『ゲド戦記』